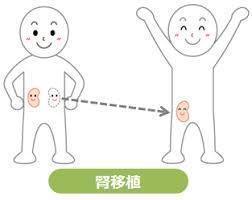労務のなるほど質問箱・賃金編

日々の労務管理におけるクエスチョンは、様々です。
このページでは、
社労士事務所を運営する中で
賃金に関する質問として寄せられた相談事例をご紹介します。
御社でも、疑問に感じていたものが有るかもしれません。
ご参考になれば、幸いです。
賃金に関する質問
興味のある質問をクリック
 算定対象期間の全期間を勤務した定年再雇用者にも賞与を支給しなければならないか。
算定対象期間の全期間を勤務した定年再雇用者にも賞与を支給しなければならないか。
 日ごとに所定労働時間が異なる日給制アルバイトの1時間当たりの金額は、どの様に成るのか。
日ごとに所定労働時間が異なる日給制アルバイトの1時間当たりの金額は、どの様に成るのか。
 育児短時間勤務を利用している社員の年次有給休暇取得時における通常の賃金とは、8時間なのでしょうか。
育児短時間勤務を利用している社員の年次有給休暇取得時における通常の賃金とは、8時間なのでしょうか。
 2つの会社で働く場合『時間外』となって割増賃金を払うのはどちらの会社に成るのでしょうか。
2つの会社で働く場合『時間外』となって割増賃金を払うのはどちらの会社に成るのでしょうか。
 深夜割増が含まれているアルバイトの時給を昼間の勤務にも適用した場合、問題がありますか。
深夜割増が含まれているアルバイトの時給を昼間の勤務にも適用した場合、問題がありますか。
 固定残業代制をとっている場合に代休の日の賃金を控除することができるか。
固定残業代制をとっている場合に代休の日の賃金を控除することができるか。
 勤務日が翌日の休日に及んだ場合、休日の割増(3割5分増)が必要となるのか。
勤務日が翌日の休日に及んだ場合、休日の割増(3割5分増)が必要となるのか。
 繁忙期にだけ支給している手当を、割増賃金の算定基礎となる賃金に含める必要がありますか。
繁忙期にだけ支給している手当を、割増賃金の算定基礎となる賃金に含める必要がありますか。
 賞与を毎月支給した場合、割増賃金の算定基礎に含めることが必要でしょうか。
賞与を毎月支給した場合、割増賃金の算定基礎に含めることが必要でしょうか。
 休職中の社員が健康診断の受診に要した時間の賃金は必要でしょうか。
休職中の社員が健康診断の受診に要した時間の賃金は必要でしょうか。
 退職までの有給消化に入っている期間の通勤手当を支給しなけれがならないか。
退職までの有給消化に入っている期間の通勤手当を支給しなけれがならないか。
 他社の休日に当社で働く場合、休日労働として割増賃金を払う必要があるのでしょうか。
他社の休日に当社で働く場合、休日労働として割増賃金を払う必要があるのでしょうか。
 勤務が翌日まで及んだ場合、どこまでを時間外労働とする必要があるのでしょうか
勤務が翌日まで及んだ場合、どこまでを時間外労働とする必要があるのでしょうか
 所定休日の割増賃金を3割5分で払っている場合、休日の振替で週40時間を超えた場合も3割5分の割増が必要ですか。
所定休日の割増賃金を3割5分で払っている場合、休日の振替で週40時間を超えた場合も3割5分の割増が必要ですか。
出張先で日をまたいで勤務した場合の日当はどうなるのか。
ある社員の出張先での勤務が午後10時から翌朝6時までで、日をまたいだのですが、
この様な場合の日当は、1日分を支払えばよいのでしょうか。
当社の出張旅費規程には、日当については、出張1日について金額が定められており
出張日数については、『出張の開始日から終了日までの日数とする。』となっています。
その為、今回は、2日分の支払が必要なのかとも思うのですが、現場からは1日分で良いのではないかと意見が出ています。
この様な場合、どの様に考えれば良いのでしょうか。
出張に伴う日当については、貴社の出張旅費規程の定めるところに依ります。

貴社の出張旅費規程では、
日当の支給基準は『出張1日につき』と定めがあることから、
出張の日数に応じて支給する事が判ります。
そして、出張の日数については、
『出張の開始日から終了日までの日数』と定めています。
そうすると、今回のご質問の場合は、出張日数が少なくとも2日となります。
当該社員は、日をまたいで勤務しており、労働時間のカウントとしては、1勤務と考える事になります。
労働時間は、日をまたぐ場合にも、始業の属する日の労働として1勤務として扱い、
その時間が法定労働時間を超える場合には、割増賃金が必要となります。
しかし、日当については、貴社の出張旅費規程では、1回の勤務について金額を定めている訳ではなく、
出張日数について、その日数に応じた金額を支給することになっています。
従って、ご質問の場合は、2日分の日当を支給することに成ります。
算定対象期間の全期間を勤務した定年再雇用者にも賞与を支給しなければならないか。
当社では、60歳の誕生日を定年として、60歳の誕生日の属する月の末日をもって退職としています。
そして、翌日からは、嘱託として再雇用しています。
また、正社員の賞与については、夏期の賞与の支給は7月としており、
算定期間は、昨年の11月から本年の4月となっています。
当社の給与規定では、賞与の支給対象者について、
『賞与の算定期間の全期間を労働し、且つ、支給日当日に在籍している正社員とする。』と定めています。
その為、算定期間の全期間を勤務した場合でも、支給日において嘱託である場合は、賞与の支給対象にしていません。
先日、6月に定年退職となり、7月から嘱託となった者から、
『算定期間の全部を勤務し、支給日に会社に在籍しているのだから、夏の賞与が支給されるのではないか。』
という話がありました。
当社の取扱いは、問題があるのでしょうか。
給与規定の文言をそのまま当てはめると、
嘱託は、賞与の対象者に該当しないと考えられる為、運用上は、問題ありません。

貴社の給与規定によれば、賞与の支給対象者については、
①『算定期間の全期間を労働』していること
②『支給日当日に在籍している正社員』
という2つの要件があります。
まず、①については、今回の対象者は、要件を満たしています。
そして、もう一つの要件である②については、
正社員ではなく嘱託として在籍しているため、要件を充たしているとは言えません。
結果として、給与規定通りに運用されていると言う事であれば、特に問題はないと言えます。
日毎に所定労働時間が異なる日給制アルバイトの1時間当たりの賃金は、どの様になるのか。
当社の日給制アルバイトは、月曜日から金曜日は1日5時間、土曜日は2時間で勤務しています。
日給は、平日も土曜日も同額で、一律5,000円を支払っています。
先日、あるアルバイトが土曜日に超過勤務が発生した為、超過時間の2時間分の賃金として2,000円を支払いました。
すると、そのアルバイトから『土曜日は2時間勤務なので、
平日の時間単価である1,000円で計算するのは、間違いではないか。』と言われました。
この様な場合、土曜日の2時間勤務を前提とした計算で支払わなければならないのでしょうか。
日給制の場合、1日の所定労働時間が一定であれば、日給をその時間で除した額で良いのですが、
日により所定労働時間が異なる場合は、日給を1週間の平均所定労働時間で除した額となります。

ご質問のアルバイトは、日により所定労働時間が異なります。
この様な場合、当該アルバイトの時間当たりの賃金は、
日給の5,000円を1週間の平均所定労働時間である、
(平日5時間×5日+土曜日2時間)÷6日=4.5時間で除する
事に成ります。
つまり、5,000円÷4.5時間≒1,111円
超過勤務については、これを基に賃金を支払うことになります。
育児短時間勤務を利用している社員の、年次有給休暇取得時における通常の賃金とは、
8時間なのでしょうか。
当社は、年次有給休暇を取得した場合『通常の賃金』を支払うことに成っています。
先日、育児短時間勤務を利用している社員から、
「うちの会社は、1日6時間の育児短時間勤務を利用していても、
年休を取得したら8時間分くれるんですね。」と言われました。
給与計算担当者に確認したところ、
「就業規則で年休取得の場合は、『通常の賃金』を支払う。
と書いているので、8時間分支払っています。」と言う回答でした。
年休取得時の『通常の賃金』とは、
この社員の言うように、8時間分の賃金なのでしょうか。
育児短時間勤務を利用している社員の年休取得時に支払う『通常の賃金』は、
6時間分の賃金です。

労働基準法では、年次休暇取得時に支払う賃金として、
①平均賃金
②所定労働時間労働した場合に支払れる賃金(通常の賃金)
③健康保険法による標準報酬日額に相当する金額
の3種類のいずれかと定めています
ただし、①②の賃金を選択することが原則とされ、
いずれを選択するかは就業規則等に於いて明確に規定することが求められています。
また、③を選択する場合には、労使協定の締結が要件となっています。
上記の様に、3つの選択肢がありますが、
一般的には『通常の賃金』で支払うのが多いようです。
ここで言う『通常の賃金』とは、年休を取得した日に元々決められた所定労働時間に対して支払われる賃金を言います。
従って、所定労働時間が8時間の貴社の場合、8時間分の賃金になります。
しかし、
育児短時間勤務を利用している社員の所定労働時間は、6時間ですので、
6時間分の賃金を支払えば良い事になります。
2つの会社で働く場合、時間外となって割増賃金が発生するのは、
どちらの会社なのでしょうか。
新たに1日6時間働くパート社員を雇用します。
本人と話をしていたところ、夜4時間ほど働いていることが判りました。
以前、2ヵ所以上の会社で働く場合、
労働時間が通算され8時間を超える場合は、割増賃金が発生すると聞いたことがあります。
この様な場合、どちらの会社が割増賃金を払う事に成るのでしょうか。
通算して8時間を超える場合の割増賃金は、新たに雇用する貴社が払う事になります。

おっしゃる様に、複数の会社で働く場合は、
労働時間は通算されます。
そして
その時間が法定労働時間を超える場合は、
その時間は、時間外労働として扱われ
割増賃金の支払いが必要となります。
この様な場合、割増賃金の支払が必要になるのは、
時系列的にあとで労働契約をした会社となります。
つまり、このケースの場合、貴社が割増賃金を払うこととなります。
深夜割増の含まれているアルバイトの時給を昼間の勤務にも適用した場合、
問題がありますか。
主に深夜の時間帯に働いてもらっているアルバイトがいます。
このアルバイトの労働条件通知書には、『時給1,300円(深夜割増を含む)』と明示しています。
このアルバイトは、通常は深夜の勤務なので時給1,300円で計算した給与を支払っているのですが、
時々、昼間の勤務についてもらうことがあり、その場合も時給1,300円で計算しています。
昼間の勤務は、大目に払っているということで問題ないと思うのですが。
深夜勤務の場合の基本部分と深夜割増部分と明確にしていないと、
時給が1,300円と受け取られることがあります。

労働条件通知書で
時給に深夜割増を含むとしていることについてですが、
含んで幾らというのは、判りにくくトラブルの原因になり得ます。
基本時給と割増分を別々に、明記するべきでしょう。
この場合、時給1,040円、深夜割増260円とするべきです。
次に昼間の勤務をしてもらった場合も、時給1,300円で『多めに』支給している点ですが、
昼間の勤務に対する時給が明確にされておらず、時給1,300円と受け取られる可能性があります。
やはり、時間給と割増分を明記して、深夜の勤務と昼間の勤務の賃金を明確に区別しておく必要があると思います。
固定残業代制をとっている場合に代休の日の賃金を控除することができるか
当社は、1日の所定労働時間を8時間。
休日に関しては、土・日・祝日としています。
所定休日に出勤させたときは25%、
法定休日に出勤させたときは35%の割増賃金を払っています。
そして、休日出勤をさせた場合には、
後日必ず代休を与えるようにし、
代休を取得した日については、1.0日分の賃金を控除しています。
ところで、
来月から月20時間分の固定残業代を支給することになりました。
対象となる時間外労働については、日々の残業だけでなく
25%の割増の付く所定休日に出勤した時間も含まれることになります。
この様に固定残業代を支給する場合、
これまでの様に代休を取得した日について、1.0日分を控除しても良いのでしょうか。
所定休日に出勤した従業員に代休を取らせた場合、代休分を控除すると給与が減額になる様な気がするのですが。
固定残業代の20時間に含まれる分は、
すでに支給している事になる為、控除することになります。

固定残業手当は、
実際に残業がない場合にも支払われる手当であり
貴社の場合には、
実際に残業した時間と所定休日に出勤した時間が
月20時間に収まる場合には、
別途賃金が発生しないことになります。
例えば、所定休日に8時間労働をさせた場合に、本来であれば8時間について25%増の割増賃金が生じます。
しかし、月20時間の固定残業手当の範囲内であるため、別途支払いが生じません。
すでに支払われていると言うことです。
一方、代休とは、休日労働や長時間労働をさせた場合に、
その代償として他の労働日を休日とするものですが、
代休を付与する義務はなく、任意に与えることができます。
そして、
代休を取得した日については、不就労であるため、ノーワークノーペイの原則により賃金を控除することができます。
このことは、固定残業手当を支給する場合も変わりませんので、
貴社の場合これまで通り代休分について控除することができます。
ただし、
所定休日の出勤については、代休分が控除されることにより、ご質問のように給与が減額されることになります。
休日出勤をしたにもかかわらず給与が減額されることは、違和感があるでしょう。
所定休日に出勤した時の手当が固定残業手当に吸収されてしまうことから
所定休日に出勤したことに対する手当が見えにくくなり、減額だけが目立つことになった訳です。
勤務が翌日の休日に及んだ場合、休日の割増(3割5分増)が必要となるのでしょうか。
当社の休日は、土曜、日曜、祝日で、日曜日を法定休日としています。
また、所定労働時間は午前9時から午後6時、休憩時間1時間としています。
先日、土曜日と月曜日を振り替えて土曜日に出勤させたところ、
業務が長引き終了が日曜日の午前3時となりました。
この様な場合、休日労働割増3割5分は必要になるのでしょうか。
御社の場合、日曜日を法定休日としている為、休日割増が必要です。

労基法上3割5分の割増賃金を支払わなければならないのは、
法定休日に労働させた場合です。
法定休日とは、週1日または4週4日の休日を言います。
御社の場合、日曜日を法定休日としていますので、
日曜日に労働させた場合、3割5分の割増の対象になります。
また、休日とは、暦日を指し午前零時から午後12時までを言います。
ご質問のケースを見ると、
土曜日の休日と月曜日の労働日が振り替えられていますので、土曜日は通常の労働日になります。
従って、土曜日に労働させても法定労働時間を超えない限り、割増賃金は発生しません。
しかし、業務が長引いて翌日曜日の午前3時に業務が終了していますので、以下の様な割増賃金が発生します。
①午後6時から午後12時まで・・・時間外労働として2割5分増し
②午後10時から翌日午前3時まで・・・深夜労働として2割5分増し
③午前0時から午前3時まで・・・休日労働として3割5分増し
繁忙期にだけ支給している手当を、割増賃金の算定基礎となる賃金に含める必要がありますか。
当社は、菓子を販売しています。
繁忙期は、お中元とお歳暮のシーズンで、非常に忙しくなることから、
この時期に勤務する販売員には、出勤1日に付き1,000円を支給しています。
最近、ある販売員から、『残業代に繁忙手当が反映されていないのは、おかしいのではないか。』と言われました。
繁忙手当は、一定の時期にだけ支給するものであり、また、販売員によって出勤日数が異なることから、
繁忙手当の支給金額がバラバラで、残業代計算の際に繁忙手当を計算の基礎には含めていません。
本来は、販売員の言うように、含めるべきものなのでしょうか。
貴社の繁忙手当は、割増賃金の算定基礎から除外できる賃金に含まれておらず、算定に含める必要があります。

残業代の計算の基礎となる賃金は、
『通常の労働時間または労働日の賃金』ですが、
労働と直接関係の薄い
個人的事情に基づき支給する賃金については、
割増賃金の算定基礎となる賃金から除外することができます。
具体的には、
①家族手当、②通勤手当、③別居手当、④子女教育手当、
⑤住宅手当、⑥臨時に支払われた賃金、⑦1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金の7種類となります。
上記の①から⑤の手当は、労働と直接関係が薄く、算定基礎から除外できる賃金として判り易いと思います。
そこで、⑥と⑦を具体的に見てみると、
『臨時に支払われた賃金』については、
臨時的、突発的事由に基づいて支払われたもの、
及び結婚手当等支給条件は、予め確定されているが、支給事由が発生が不確定であり、
かつ、非常に稀に発生するものをいう。(昭22.9.13発基第17号)
『1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金』については、
賞与および1ヵ月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当、
1ヵ月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当、
1ヵ月を超える期間にわたる事由によって算定される
奨励加給または能率手当を言うものとされています。(労基法施行規則第8条)
賞与を毎月支給した場合、割増賃金の算定基礎に含めることが必要でしょうか。
当社では、年2回、7 月と12 月に賞与を支給していますが、
今後、営業職については、毎月の営業成績に応じて、賞与を支給することを検討しています。
この場合、支給基準に達すれば、最大、年12 回の賞与が支給されます。
ところで、先日、賞与を毎月支給すると、割増賃金の算定基礎に含めなければならないということを聞きました。
今まで、賞与を割増賃金の算定基礎に含めたことはありません。
同じ賞与であっても、毎月支給する場合は、割増賃金の算定基礎に含めなければならないのでしょうか。
ご質問の賞与は、割増賃金の算定基礎から控除される賃金に含まれません。

労働基準法第37 条の定めにより、
割増賃金は、通常の労働時間または労働日の賃金を基礎として
算定しなければならないと定められています。
ただし、
家族手当、通勤手当、その他厚生労働省令で定める賃金は、
その基礎となる賃金から除外されています。
そして、
除外される賃金には、家族手当、通勤手当のほかに別居手当、子女教育手当、住宅手当、
臨時に支払われた賃金および1 ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金が掲げられています。
これらの賃金は単なる例示ではなく、制限的に列挙されているものですので、
これらに該当しない賃金はすべて割増賃金の基礎となる賃金となります。
そして、除外される賃金のうち、
1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金には、賞与と以下の手当があります(労働基準法施行規則第8 条)。
① 1 ヵ月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当
② 1 ヵ月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当
③ 1 ヵ月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給または能率手当
したがって、現在のように、年2 回支給されている賞与の場合は、
1 ヵ月を超える期間ごとに支払われている賃金に該当しますので、
割増賃金の基礎となる賃金に含める必要はありません。
一方、
今後、毎月支給される賞与に変更した場合については、その支給額を決定する評価期間は1 ヵ月とのことであり、
また、
最大12 回、毎月支給されることがあることからしても、1 ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金に該当しません。
休職中の社員が健康診断の受診に要した時間の賃金は必要でしょうか。
先日、療養により休職中の社員から、健康診断を受診したいという申出がありました。
定期健康診断を実施している期間に休業をしている場合、
通常は、復職した後で健康診断を受診させているのですが、
今回、本人から希望があったので、休職中ではありますが、受診させようと考えています。
そこで、健康診断の受診に要した時間の賃金の取扱いについてお聞きします。
通常は、就業時間中に健康診断を受診してもらうようにしており、健康診断の受診に要した時間を労働時間として扱い、
健康診断に要した時間の賃金を控除することなく支払うという取扱いをしています。
しかし、
今回、休職中の社員に対しては、健康診断の受診に要した時間の賃金を支払わないという取扱いをしようと考えています。
通常と異なる取扱いをすることに問題はありますか。
健康診断の受診に要した時間の賃金に付いては、支払っても支払わなかっても構いません。

健康診断の受診に要した時間についての賃金の支払いについては、
「労働者一般に対して行なわれるいわゆる一般健康診断は、
一般的な健康の確保をはかることを目的として
事業者にその実施 義務を課したものであり、
業務遂行との関連において行われるものではないので、
その受診のために要した時間については、
当然には事業者の負担すべきものではなく、
労使協議して定めるべきもの」とされています。
(昭47.9.18 基発第602 号)
したがって、
療養により休職中の社員が健康診断に要した時間について、賃金を支払っても支払わなくても差し支えありません。
ところで、通常は、就業時間中に健康診断を受診させることにより、健康診断の受診に要した時間を労働時間として扱い、
その時間について賃金を支払う扱いをしているとのことですが、休職中は就業をしておらず、
また、今回は、休職中の本人からの希望で、健康診断を実施する手配を進めていることからすれば、
健康診断の受診に要した時間の賃金の取扱いに、通常の取扱いと違いがあっても、特に問題にならないと考えます。
退職までの有給消化に入っている期間の通勤手当は支払わなければならないか。
来月末で退職する社員が、明日から30 日間の年次有給休暇の消化に入ります。
今日が最終出勤日なのですが、このような退職までの有休消化の期間中についても、
通勤手当を支払わなければならないものでしょうか。
就業規則では、有休を取得した日の賃金については、
所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払うとし、
通勤手当については、1ヵ月の定期券相当額を支払うと定めています。
なお、通常は、有休を取得した日については、通勤手当を含めて、特に賃金を控除することなく支払っています。
就業規則等で、実際の通勤がないケースについて記載がない場合は、支払う必要があります。

退職時の有給給休暇の消化期間中の通勤手当の取扱いについては
就業規則に通勤手当のルールをどのように定めているかによります
通勤手当については、
法的に支払わなければならないものではありませんので、
支払うかどうかを含めて、会社が自由に決めることができます。
したがって、支給しないとすることもできます。
支給する場合にも、実費を支給すること(アルバイトに多くみられます。)や、
上限額を決めて支給するといったことも可能です。
貴社の場合は、通勤手当については、1ヵ月の定期券相当額を支払うと定めているだけで、
実際に出勤がなかった場合の取扱いについて特に定めがないようです。
したがって、
ご質問のケースの場合、退職までの有休消化の期間においても通勤手当を支払わなければならないと考えます。
一般に、月給者が有休を取得した場合には、出勤したものとみなして、給与計算上、そのままの額を支払います。
ところが、退職前の有休消化の際には、有休消化の日数によっては、一給与計算期間に全く出勤がないこともあり、
そのようなときにまで通勤手当を払わなければならないかと相談を受けることがあります。
通勤手当は、通勤に対して支払うものであり、通勤という事実がないときにまで支払う必要はないと考えます。
そこで、有休消化に限らず、一給与計算期間に、現実の出勤日数が一定の日数を下回ったときには、
実費を支給する旨を就業規則に定め、
結果として、現実の出勤が1日もない場合には通勤手当を支払わないとすることも考えられます。
他社の休日に当社で働く場合、休日労働として割増賃金を支払う必要があるのでしょうか。
週2日働くアルバイトが、他の会社で働いており、その会社の休日に当社で勤務していることがわかりました。
そのため、当社で週2日働くことにより、週40 時間の法定労働時間を超える場合は、
時間外労働として割増賃金を支払うことを伝えたところ、
「他社の休日に働いているので、休日労働としての割増賃金を支払ってほしい。」と言われました。
本人が言うように、休日労働の割増率を加算した賃金の支払いが必要になるのでしょうか。
また、2社で働くことにより、週1 回の休日も確保できていないことも気がかりです。
「休日」については、異なる事業場における休日を通算するという 規定は存在しません。

事業場を異にする場合においても、
「労働時間」に関する規定の適用については、
通算すると規定されていますが、
「休日」については、異なる事業場における休日を通算するという
規定は存在しません。
そのため、他の事業場の休日に貴社で労働したとしても、
「休日」に労働させたことにはならず、
休日労働の割増賃金を支払う必要はありません。
つまり、貴社のアルバイトについては、他社での労働時間を申告させ、通算した時間が法定労働時間を超えた場合、
超えた時間に対し、2割5分で計算した割増賃金を支払えばよいことになります。
また、週1回の休日も確保できていない点についてですが、
貴社とアルバイトとの労働契約は週2日の勤務であるため、
週1 日以上の休日は、確保されていることになりますので、
貴社が休日を付与していないということにはなりません。
しかしながら、こうした兼業は、
結果的に長時間労働となり、疲労が蓄積し、本人の想像以上に心身への負担がかかると考えられます。
政府も健康障害防止を目的とした長時間労働の監督指導を強化しているところですので、
実際に週1回の休日も確保できていないことは、貴社で休日を与えているかどうかということにかかわらず、
労働災害防止や業務効率の観点からも望ましいとはいえないため、極力このような労働契約は回避すべきものと考えます。
勤務が翌日まで及んだ場合、どこまで時間外労働とするべきでしょうか。
先日、10 時から19 時を通常の勤務としている者が、緊急の業務に対応するため、19 時以降も勤務し、
そのまま翌日の12 時まで勤務しました。
給与計算にあたり、19 時から翌日の始業時刻である10 時までを時間外(1.25)、
22 時から翌日の5 時までを深夜勤務(0.25)として計算しようとしたところ、
担当者が今回のようなケースについてネットで調べ、
「勤務が翌日に及んだ場合、当日の勤務の継続となるので、翌日の12 時までが時間外労働になる」
という情報を見つけたらしく、時間外は翌日の10 時まででなく、
勤務を終了した翌日の12 時まででないかといってきました。
翌日は通常の労働日であり、勤務が翌日まで及んだ場合は、翌日の始業時刻までが当日の勤務となり、
時間外労働の対象となると考えていたのですが、どうなのでしょうか。
翌日は通常の労働日であり、10 時には翌日の勤務が開始されますので、
翌日の10 時で当日からの勤務は終わることになります。

労働基準法における1日の考え方については、行政通達で、
「午前0 時から午後12 時までのいわゆる暦日をいうもの」とされ、
2暦日にわたる勤務については、
「たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、
当該勤務は、始業時刻の属する日の労働として、
当該日の『1日』の労働とすること」とされています。
そのため、ご質問にあるように、
翌日の勤務は、当日の始業時刻から継続した勤務となります。
それでは、この当日から継続した勤務がどこまで続くかですが、
翌日は通常の労働日であり、10 時には翌日の勤務が開始されますので、
翌日の10 時で当日からの勤務は終わることになります。
したがって、当日の時間外労働として扱うのは19 時から翌日の10 時までとなります。
また、翌日の10 時から12 時までは、翌日の勤務となり、通常の賃金を支払えばよいことになります。
所定休日の割増賃金を3割5分で払っている場合、
休日の振替で週40時間を超えた場合の割増も3割5分が必要ですか。
当社では、所定休日に勤務した場合、3割5分の割増賃金を支払っています。
先日、振替休日による割増賃金の発生に気づかず、遡ってその清算(割増賃金部分のみ)をすることになりました。
そこで、振り替えた週の労働時間が週40 時間を超える週の労働時間を集計し、
2割5分の割増賃金を算出したところ、
所定休日に勤務(週40 時間を超える時間外労働)した場合、
3割5分で割増賃金を支払っているので、
振り替えによって生じた時間外労働についても、
2割5分ではなく3割5分の割増賃金を支払う必要があるのではないかという意見が出ています。
この場合、2割5分と3割5分、どちらの割増率で支払うべきでしょうか。
就業規則に於いて、週40時間を超えた時間については、3割5分を支払うと決めてなければ必要はありません。

振替休日により休日と労働日を振り替えたことにより、
週40 時間の法定労働時間を超えるときは、超えた時間について、
2割5分以上の割増賃金の支払いが必要となります。
ご質問では、所定休日に3割5分の割増賃金を支払っているため、
振り替えにより週40時間を超えた時間についても、
同様の割増賃金を支払うべきという意見が出ているとのことです。
この点については、
貴社において、週40 時間を超えた時間について3割5分の割増賃金を支払うと定めているのであれば、
3割5分の割増賃金を支払わなければなりませんが、
そのような定めがないのであれば、3割5分の割増賃金を支払う必要はありません。
そのため、振り替えによって所定休日が労働日となったことにより、
週40 時間を超えた労働については、法定通り2割5分以上の割増賃金を支払えばよいということになります。
法定休日と翌週の月曜日を振り替えて、振替休日となったその月曜日に出勤を命じた場合、
月曜日の出勤に対する割増率はどうなるのか。
当社の休日は、日曜日(法定休日)、土曜日、祝日としており、週の起算日は日曜日です。
先日、ある社員について、第1週の法定休日である日曜日と第2週の月曜日を振り替えて、
日曜日を出勤日、月曜日を休日としたところ、緊急の事態が発生し、月曜日に出勤してもらうことになりました。
この場合、第2週の振替休日であった月曜日の出勤に対する割増率はどう考えればよいのでしょうか。
法定休日は、週1回必要であるため、 貴社のように法定休日を特定している場合、
法定休日(日曜日)を翌週の労働日(月曜日)と振り替えると いったことはできません。

労働基準法では、
週1回または4週4日の休日を法定休日としています。
法定休日は、週1回必要であるため、
貴社のように法定休日を特定している場合、
法定休日(日曜日)を翌週の労働日(月曜日)と振り替えると
いったことはできません。
第1週の土曜日が休日であり、
休日そのものは1日確保されているため、問題がなさそうにみえますが、
法定休日が週1回確保されていなければならないため、
法定休日である日曜日を翌週に、週をまたいで振替をすることができないことになります。
それでは、ご質問のような場合、割増賃金がどうなるかですが、
まず、第1週の日曜日の出勤が法定休日の出勤となり、休日割増(3割5分増以上)が必要となります。
一方、休日の振替により、
休日のはずが緊急事態の発生によって結果的に出勤することになってしまった第2週の月曜日については、
第2週の日曜日と土曜日が休めているのであれば、通常の労働日と変わらないことになります。
つまり、第2週の月曜日の出勤については、特に割増賃金が発生しないことになります。
年次有給休暇を取った月も皆勤手当てを払わなければならないか。
当社は、皆勤手当として月額5,000 円を支給しています。
先日、社員から「年次有給休暇を取得したことで、皆勤手当が支払われないのはおかしい。」と言われました。
年次有給休暇を取得した場合、実際に勤務しているわけではないので、
皆勤手当を支払わなくてもよいと考えていましたが、まずいのでしょうか。
皆勤手当を支払わなければなりません。

皆勤手当は、遅刻・早退・欠勤を予防することを目的として、
賃金計算期間の勤務が無遅刻・無欠勤だった従業員に支払われる
手当です。
「皆勤手当」や「精勤手当」「精皆勤手当」などの手当名で
支払われていることもあります。
貴社のように、賃金計算期間の間に年次有給休暇を取得した場合、
実際に勤務していないため、皆勤手当を支払わないとすることは、一見、問題がないようにみえます。
しかし、労働基準法では、
年次有給休暇を取得した労働者に対し、賃金の減額その他不利益な取扱いをしてならないと規定しています。
なぜなら、年休を取得することによって労働者に対し不利益な取扱いをすれば、
年休取得が抑制されてしまい、年休取得の本来の目的である心身の疲労回復や労働力の維持培養が図れなくなるからです。
裁判例においても、皆勤手当等の諸手当の全部または一部を
「年休を取得した休んだことのある日」を理由にして
支給しないこととすることは、
不利益な扱いとして許されないとしているものがあります。
(昭51.3.4 横浜地裁判決「大瀬工業事件」)
以上のことから、年次有給休暇を取得したことで皆勤手当を支払わないとすることは、
不利益な取扱いとなることから、貴社は皆勤手当を支払う必要があります。
なお、皆勤手当は、必ずしも毎月発生する手当ではないことから、
割増賃金の計算の算定基礎となる賃金から除外されていることがあります。
しかし、割増賃金の算定の基礎から除外される賃金は、家族手当や通勤手当などに限定されており、
皆勤手当は、除外される賃金に該当しないため、
割増賃金を計算する際には算定の基礎とする必要があります。
慶弔休暇やリフレッシュ休暇、記念日休暇などといった会社独自の休暇制度を設けている場合、
皆勤手当をどのように取り扱うかについて検討しておくとよいでしょう。