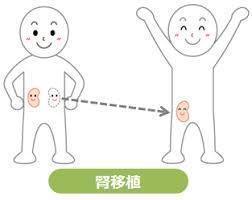総合評価型人事制度

人事制度の重要性については、
多くの経営者様が異口同音に口を揃えられます。
適正な人事制度は、従業員のモチベーションアップや
能力の向上に繋がり、
その事は、企業業績に直結します。
御社は、従業員の何を評価して居られますか。
当事務所は、『役割主義』『能力主義』『成果主義』に偏重した評価制度を廃し、
それぞれを調和させた『総合評価型人事制度』を提唱しています。
人事評価制度の予備知識

人事評価制度とは、
1年間もしくは半年・四半期等、一定期間の社員の労働に対する評価を実施し、給与の昇給額や賞与の額に反映させることです。
さらには、
昇進・昇格に反映させる制度のことを指します。
主に「評価制度」「賃金制度」「昇進昇格制度」の3つの仕組みで構成されています。
近年、人事制度の見直しに伴い、成果報酬制度や多面評価制度など、
様々な工夫を凝らした人事制度を導入する企業が増加してきています。
かつて多くの企業が運用していた、終身雇用前提の年功序列型人事制度では、
評価、昇進・昇格の基準は、
年齢や勤続年数など、比較的わかり易い項目に基づいて決定・運用されていました。
しかし、成果主義を取り入れる企業が増加するにつれて、
評価制度の透明性や公平性が求められるようになりました。
その表れとして、
具体的な行動をもとに評価するコンピテンシー制度や各プロセスの達成度合いを量る、
目標管理(MBO)制度などを、導入(もしくは両者を併用)する企業が増えてきています。

「社員に対し、会社が向かう方向性を理解・浸透させ、社員が成長しながら最大限の能力を発揮することで、 会社の業績を向上させる」ことです。
ただ単に賃金や賞与を決めるためだけのものではありません。お金やポストだけで「やる気」を引き出すのには限界があります。
人材の能力を最大限に発揮させる人事制度には、
①公平かつ納得感のある評価の実現
②役割と目標の明確化
③社員のキャリアプランの明確化
④社員のモチベーションアップ、の4つの要素が必要なのです。
社員の貢献度に見合った処遇を実現させることで、高い成果を上げた社員が報われる、納得性の高い人事評価制度を作り、社員を活性化させていくことが重要です。
この評価制度の目的と内容が、社員に正しく理解され、徹底した運用ができていれば、人事に対する不満はほとんど出てこないはずです。
そのためには、行動理念や戦略、人材育成の目標や課題等を落とし込み、会社が求める方向に 社員が育ってくれるように、評価の基準を定める必要があります。
逆に間違った方向性、内容で評価基準を作成してしまうと、評価結果はそろって良い結果なのに業績は低迷したまま、という現象が発生してしまいます。
そのようなことにならない為にも、
人事評価制度は、社員が主体性をもって成長できる就業環境の実現の為に、社員のやる気を引き出す、評価基準・仕組・環境を整えることが重要です。
従来の評価制度の概要

企業では限られた人件費原資をいかに配分し、企業業績向上、組織活性化に結び付けていくかが問われています。
配分の為の基準には、『能力』『役割』『成果』が有ります。
これらに着眼した人事制度を、
『能力主義人事制度』
『役割主義人事制度』
『成果主義人事制度』と言います。
(1)能力主義人事制度
能力主義は、その人の持つ能力で、処遇を決める考え方です。わが国で最も広く導入されている人事制度で、文字通り能力評価を行います。
等級は能力の発展段階を表すものと捉え、等級・号俸による賃金表を使用して、賃金管理を行います。一旦身につけた能力は、減退しないものと考え、基本的には降格はありません。しかし、知識の陳腐化の激しい今日、違和感を覚える従業員は多い事でしょう。
役割主義の様に役割が変わっても、直ちに等級が変わると言う事はなく、賃金も確保される為、組織変更や人事異動を柔軟に行う事が出来ると言う特長があります。
しかし、実際に能力を直接評価する事は、極めて難しい事です。
従って、行動・結果から能力を間接的に評価する事に成りますが、それでもなお能力主義による評価は難しい為、評価基準が曖昧になりがちです。
(2)役割主義人事制度
役割主義は、その人の役割に基いて処遇する考え方です。評価は、目標管理と行動評価によって行います。役割と等級がリンクしており、賃金は等級に対応して設定されます。
等級は、役割のレベルによって設定される為、等級基準に付いての説明は、明確に行なうことが出来ます。役割が変わった時に、等級、賃金をどうするのかと言う問題が生じます。
賃金は等級に応じて設定され、基本給に付いては等級間のダブりを認めない例が多いようです。その結果、上限・下限の幅が狭くなり、同等級の滞留期間が長くなると、すぐに上限に達してしまいます。
(3)成果主義人事制度
成果主義は、その人の評価を成果で行なうことと、賃金による動機づけが特長です。
成果の評価には、目標管理の評価を使う例が多いようです。会社の目標、部門の目標から各自の目標を明確にして、その結果で評価する為、会社にとっても、個人にとっても、判りやすい制度だと言えます。
しかし、多くの企業で取入れた結果、以下の様な問題が指摘されています。
①管理部門や製造部門のように、業務の成果が数字に表れ難い部署では評価が難しい。
②短期的な成果を上げる事に熱心になり、長期的成果についてなおざりに成りやすい。
③目標管理で低めの目標を掲げがちである。
④個人の成果が重要視され、チームワークが軽視されやすい。
⑤管理職が自分の成果に腐心し、部下の育成をなおざりにする傾向がある。
実際に取り入れた多くの企業が、廃止せざるを得ませんでした。
総合評価型人事制度とは

これからの人事制度は、能力、役割、成果という、
それぞれのファクターの特質を生かし、
バランスを取って運用する事が必要です。
その為には、
『能力、役割、成果とは何か。』を明確にして、
これらをどのように評価するのかを、明らかにしなければなりません。

能力の特質としては、
『保有』と『再現性』が挙げられます。
能力は保有しているものですから、
ある一定の時点において、
保有している事を評価することになります。
一定期間の行動や結果を評価する『成果の評価』とは、ここが異なります。
人の能力に付いては、ハーバード大学ビジネススクールのロバート・カッツ教授の唱える 三つの能力に分類するのが分りやすいと思います。
■『テクニカルスキル』:業務を遂行するうえで、必要な知識やスキルを言う。
■『ヒューマンスキル』:人間関係を管理するスキルを言う。
■『コンセプチュアル・スキル』:物事を理論化・体系化する能力を言う。
総合評価型人事制度では、
テクニカルスキルは、知識・技能に限って『能力の評価』します。
ヒューマンスキルとコンセプチュアル・スキルについては、
スキルを発揮した行動の結果として『業績(成果)の評価』のなかで評価します。

役割とは、あるべき姿(期待像)を示す事です。
課長であれば、あるべき課長像があり、
その課長像が『課長の役割』になります。
総合評価型人事制度では、
あるべき姿をどれだけ示す事が出来ているのかを評価します。

成果とは、
『期待される役割をいかに果たしたか』と言う事です。
果たした内容は、行動・結果に表れますので、
この『行動・結果』を評価するのが成果の評価です。
しかし、成果を把握する事も、実は容易ではありません。
成果を評価する時、
目標管理では、目標以外の仕事が見えなくなる現象が現れます。
目標以外が見えづらくなるのは、『仕事の焦点化と運用の焦点化』が起こるからです。
目標は、本人が行う仕事の特定化された部分であり、それは、クローズアップされます。
一方、目標以外の仕事は、それと対比して関心が薄れ、見えなくなってしまいます。
目標は、特定化、焦点化されていますのでクローズアップして見えます。
ですから『虫の目』で見るようにします。
目標以外は、広い視野で本人の仕事が見渡せ、かつ漏れなく把握できるよう
『鳥の目』で見るようにします。
これを、総合評価型人事制度では、
「正確度」「迅速度」「仕事の質と量」「チークワーク」といった
『人事評価項目』で把握します。

これからの人事制度は、前述したとおり、
『能力の評価』『役割の評価』『成果の評価』
これらを調和させたものでなければ成りません。
ひとは、御社発展の原動力です。
大事な原動力である従業員に対しては、
公平で納得性の高い、人事制度を提供しなければなりません。
当所は、御社の実情にあった『総合評価型人事制度』を提案したいと考えております。