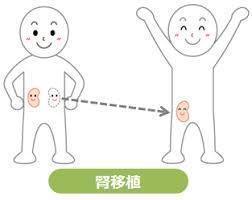新規開業者のご支援『新規開業お助けパック』とは、

御社の実情に合った就業規則と
雇用契約書、法定3帳簿などの
労務管理書式一式を提供します。

社会保険・労働保険の適用手続や
雇用した従業員の資格取得手続を
当事務所が代行サービスします。

人を雇用すると、様々なルールを
守ることを義務付けられます。
労務管理の基礎知識を提供します
激安特別価格 で、助かる3点セット提供
≪但し、開業3年まで、北九州周辺地区だけの限定サービスです。≫
●更に、労務管理知識の提供、尚、就業規則不要の場合は、半額で賜ります。

意気揚々の新規開業。
事業の成功を信じて事業計画を練り、開業資金を捻出して、誰もが熱い一歩を踏み出す事でしょう。
その時、何人の経営者が労務管理の重要性に気付いて正しい対応をしているでしょうか。
法人として起業した場合は、ただちに社会保険に加入しなければなりません。
個人として開業した場合でも、従業員をひとりでも 雇ったとたんに、労働保険の手続きが必要になります。
そればかりか、就業規則などの会社のルールや、雇用契約書などの労務管理書式を整備して、事業運営しないと、思わぬトラブルに巻き込まれる事が有ります。
そのような事になれば、事業運営どころでは、ありません。
当事務所の『新規開業お助けパック』は、
創業間もない事業主に対して、
就業規則・雇用契約書などの、事業運営にはかかせない書類を提供するとともに、
従業員を雇う事によって必要となる、当初の保険手続を代行するものです。
更に、当面必要な労務管理に関する予備知識を提供します。
多忙な日々を送る開業当初の事業主にとっては、うれしいサービスだと思います。
順風満帆の事業運営を実現する為にも、『新規開業お助けパック』をご利用ください。
採用に関する基礎知識

事業運営に於いて『ひと』『かね』『もの』の手配は避けて通れない問題です。
なかでも『ひと』の手配は、誰しも難しい課題です。
人口減少時代の我が国においては、これからの10年間で、400万人もの労働力人口が減少すると、言われており既に労働者の争奪戦が激しさを増しています。
大手企業は、あらゆる手法を駆使して、従業員の囲い込み行なっています。
あおりを受けて中小企業の従業員確保は、かつてない程、厳しい状況にあります。
一方、人材難に付け込んだブラック斡旋業者や不良社員の増加も、中小企業事業主の頭を悩ませています。
ひとが欲しいからと言って、安易な採用をすると、とんでもないトラブルに巻き込まれる事もしばしばです。
まずは、的確な雇用手続を踏まえて、人材を確保することから始めましょう。
採用計画の作成

採用計画とは、採用数を、社員の職制別、職務能力別に確定する為の計画です。
いつまでに必要なのか。
どの職務に何人必要なのか。
必要とする年齢層は、どうか。
正社員か、パート社員か、有期契約社員か。
どの程度の能力、技術等を必要としているのか。
どの様な基準で、どの程度の賃金を払うのか。
即戦力として経験者を募集するのか、未経験者を育てるのか。
これらを、総合的に勘案して、採用計画を作成したいものです。
募集

募集方法には、求人誌、ハローワークを活用するケース会社のホームページに掲載する方法があります。
求人誌による募集は、イラストや写真などの掲載により会社のイメージを良好なものにする効果があります。
ハローワークは、何と言ってもその費用が無料であることが魅力ですが、求人票の記載の仕方について、豊富な事例を基に、アドバイスを受けられると言う魅力もあります。
また、記載事項について関係法令に基づく指導が得られることで、求職者とのトラブル防止の効果もあります。
そればかりでなく、助成金に結びつく事もあります。
最近は、創業に合わせて会社のホームページを立ち上げる企業も増えています。
ホームページでの募集は、会社の詳細情報を伝えられるほか、いつでも作成変更できるのが魅力です。
最近の若者は、就職活動をするとき、まず企業のホームページで確認して応募を決めるのが一般的な行動パターンになっています。
費用対効果を考えて、自社に合った募集方法を選択したいものです。
当事務所では、ハローワーク以外の募集方法を選択した場合でも、必ずハローワークの募集も並行して継続することを推奨しています。
面接

応募があれば、いよいよ面接です。
求職者は、不安や期待を胸に秘めて訪れます。
面接場所は、求職者と面接担当者が、落ち着いて話せる場所を設定しましょう。
求職者は、これから働くかも知れない会社の応対や、社内の雰囲気を、細かく観察しています。会社全体で、求職者を気持ち良く迎えられる体制を整えましょう。
面接時には、募集内容に誤解が生じないよう、労働条件に付いて再度説明しましょう。また、事前に面接シートを作成して、確認漏れを防止しましょう。
求職所も一生懸命、会社を観察しています。面接者もしっかり観察しましょう。
複数で面接する場合は、質問項目の役割分担も決めておきましょう。
これから会社を支えてくれる人材に成長してくれるかも知れません。
ここが正念場です。
雇用契約

雇用条件を十分に確認し合って合意を得ると、雇用契約締結です。
しかし、ここで忘れてはならない事が有ります。
雇用契約を締結する際は、書面をもってその労働条件を明示しなければならない項目が決められています。
口頭で了解を取っているから書面は必要ないと言う方がいますが、今は、それでは、いけません。
雇用契約書に主な労働条件を記載して、しっかりと雇用契約書を交わしましょう。
労働条件の明示事項には、絶対的明示事項と相対的明示事項があります。
絶対的明示事項とは、書面で通知しなければならない項目で以下が決められています。
①労働契約の期間に関する事項
②就業の場所および従事する業務に関する事項
③始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日
、就業時間の転換に関する事項
④賃金の決定・計算および支払方法、賃金の締切および支払の時期、昇給に関する事項
⑤退職に関する事項(解雇の事由を含む)
相対的明示事項とは、実施するのであれば記載しなければならない事項ですが、通知は口答でも構いません。
①退職手当、随時支払われる賃金、賞与等、最低賃金に関する事項
②労働者に負担させる食費、作業用品などに関する事項
③安全および衛生に関する事項
④職業訓練に関する事項
⑤災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項
⑥表彰および制裁に関する事項
⑦休職に関する事項
さらに、パートタイマーとして契約する場合は、以下の項目が追加されます。
①昇給の有無
②退職手当の有無
③賞与の有無
④苦情相談窓口の有無
雇用状況の不安定なパートタイマーには、より詳細な明示が必要と言う事です。
これらのルールを逸脱して雇用契約を結んでしまうと、事業主は、紛争が生じたとき、大変なリスクを背負う事に成ります。
これを避ける為に、
当事務所では、これらの明示事項を網羅した雇用契約書を提供しています。
採用

いよいよ採用した従業員が出社して来ます。
事業主としては、これから右腕左腕になってもらう人材です。喜びが隠せない事でしょう。
まずは、入社時の提出書類を確認しましょう。
①入社誓約書
②身元保証書
③住民票記載事項の証明書
④源泉徴収票(入社の年に、給与所得の有った者)
⑤年金手帳(既に所持している者)
⑥雇用保険被保険者証(既に取得している者)
⑦給与所得の扶養控除等(異動)申告書
⑧健康保険被扶養者届(被扶養者を有する者)
⑨通勤経路図
⑩運転免許証・車検証・任意の損害賠償保険の写し(車輌通勤を希望する者)
⑪給与振込先届兼振込同意書
⑫各種資格証明書
⑬その他会社が必要とするもの
如何ですか、ひと口に入社書類と言っても様々あると思いませんか。
これは、一般的な企業の入社書類の例です。
特にしばりがある訳ではありませんが、
御社も出来るだけこれに準じて提出させることを推奨します。
社会・労働保険の手続

さて今回採用した従業員の所定労働時間は、週何時間でしょうか。
一般的には、週40時間働いていただく従業員を正社員と呼びますが、フルタイムパート、と言う言葉もありますので、週40時間で働いていただくパート社員もいます。
この様な従業員の保険加入については、職制に係らず、以下のルールが有ります。
●所定労働時間が週20時間未満の従業員・・・労災保険のみ加入
●所定労働時間が週20時間~30時間未満の従業員・・・労災保険と雇用保険に加入
●正規従業員に対して、所定労働時間が3/4以上で所定労働日数も3/4以上の従業員
・・・労災保険、雇用保険に加えて社会保険にも加入します。正規従業員は無論です。
ちなみに、労災保険には、アルバイトも加入します。保険料は、全額事業主持ちです。社会保険とは、健康保険、介護保険、厚生年金保険を指します。こちらは労使双方で、保険料を負担します。
●労災保険の手続きは、労働基準監督署
●雇用保険の手続きは、ハローワーク
●社会保険の手続きは、年金事務所が担当です。
当然、それぞれで保険加入の手続きをするのですが、その為には、事業所も保険の適用手続きをしなければ成りません。
事業所(会社)は、それぞれの保険の適用事業所に成る手続きが必要ですし、同時に、従業員は、それぞれ該当する保険の、被保険者資格を取得しなければなりません。
今回『新規開業お助けパック』をご注文いただいた事業所様は、
当事務所がこの手続きを代行させて頂きます。
法定3帳簿

労働者名簿、出勤簿、賃金台帳
これら3つの書類を、法定3帳簿と言います。
つまり法定ですから、法令で必ず作成する事を義務付けられている、労務管理の必須書類と言う事になります。
●労働者名簿は、労働基準法107条で事業場ごとに作成し、備え置く事が義務付けられています。
労働者名簿の記載事項は、労働者ごとに以下の項目が必要です。(日雇を除く)
①氏名
②生年月日
③履歴
④性別
⑤住所
⑥従事する業務の種類(常用労働者30人未満の事業所は不要)
⑦雇入れの年月日
⑧解雇または退職の年月日およびその理由
⑨死亡年月日およびその原因
この内、①②④⑤⑥⑦の項目をまず記載して、名簿を作成、保管します。
●賃金台帳は、労働基準法108条で、事業場ごとに調製し賃金の支払いの都度、遅滞なく各労働者ごとに記入する事とされています。
賃金台帳の記載事項は、以下の通りです。
①氏名
②性別
③賃金の計算期間
④出勤日数
⑤労働時間数
⑥時間外労働、休日労働、深夜労働を行なった時間数
⑦基本給、手当、その他賃金の種類ごとにその額
⑧賃金の一部を控除した場合は、その額
●出勤簿は、労働時間数等を確認する為の帳簿です。会社には、従業員の労働時間数等を把握することが義務付けられています。
しかし、出勤簿に付いては、他の法定帳簿と違って、何を記載すべきかとか、どうゆう方法で労働時間数を把握するのかと言った事は、労働基準法では特に定めていません。
ただし、
厚生労働省による通達
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」により、
- 使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること
- タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること
のどちらかの方法によって、労働者の始業時刻・終業時刻を確認・記録することが原則とされています。
これらの法定3帳簿を作成する事で、はじめて従業員の労務管理がスムーズに出来る様になります。
まずは、これらの書類の記載を習慣化しましょう。
労基署の監督

労働基準監督署の監督が入った時、必ず提出を求められる書類が、まさに法定3帳簿です。
先述したように法定帳簿ですから、作成して居なければそれだけで、労基法違反を指摘されます。
勿論、記載の内容、ルールに不備があれば、その是正も求めれる事になります。
労災保険や雇用保険の未加入があれば、遡及加入つまり遡って加入して、その保険料を納めることを求められる事もあります。
日頃から、労務管理書類の作成を励行して、習慣化することが非常に大事です。
当事務所が、各種労務管理書類のデータを提供して、作成を指導します。
助成金の受給

特に創業間もない事業主に取って、助成金は強い味方になります。
例え、50万円でも100万円でも、返済不要の事業資金と言われる助成金は、本当に有り難いものです。
しかし、助成金は国のお金です。
法令を守っていない企業には、助成金は支給されません。
つまり、適正に労災、雇用、社会保険に加入していることが必要です。
助成金の支給の申請をするとき必ず求められる添付書類が、
法定3帳簿である労働者名簿賃金台帳、出勤簿です。
これに、就業規則や雇用契約書、その他の書類を添付して助成金の申請をします。
助成金を受給する為にも、労務管理書類の整備は、重要な事だと理解して下さい。