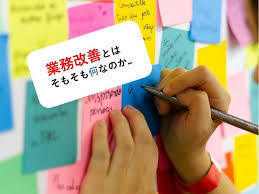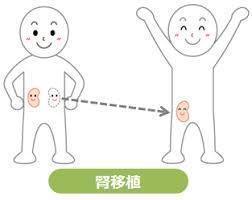令和7年度・雇用関連助成金情報について

効果的助成金申請代行と聞いて、
どんな印象をお持ち でしょうか。
それよりもまず、御社は、助成金を活用して居られますか。
助成金は星の数ほどあります。
それは、各省庁、都道府県等の行政機関、各種団体など沢山の組織が、
助成金・補助金と言う名で業務の推進を計っているからです。
ただし、ほとんどの助成金は、応募者の中から数社が選抜される、
つまり、選ばれなければ、何の見返りも無い助成金です。
しかも選抜式の助成金は、
意外にそのハードルが高く、準備の為の負担は半端ではありません。
実は、当所が扱う助成金は、選抜制のない厚生労働省の雇用に関する助成金です。
その理由は、厚労省の助成金は、一定の要件を満たせば、必ず支給されるからです。
勿論、国のお金から支給されるのですから、最低限守らなければならないルールが有り、
『誰でもどんな状況でも、簡単に獲得できる。』と言ったものではありません。

しかし本来の助成金の目的を理解し、
受給の為の要件・ルールをきちんと守って申請すれば
必ず受給できるものです。
実は、厚労省の助成金に限定しても、その種類は50種類近く作られています。
その中でも、手続の手間が程々ですみ、
かつ、数十万円以上の単位で支給されるものを、当所は厳選して取り扱っています。
ちなみに、中小企業に於ける助成金の活用率は、40%~50%程度となって居ます。
つまり、残りの企業は助成金の活用が出来ていません。
しかも、多くの場合、助成金に関する情報そのものが、届いていません。

厚労省助成金の原資は、
皆さんが納めている雇用保険料です。
どうゆう事だか、お解りになりますか。
雇用保険料の計算式を思い出してください。
雇用保険の料率は、労働者負担分と同額の事業主負担分が有ります。
そして、
事業主負担分には、更に『雇用保険二事業の保険料』と言うのが追加されて徴収されます。
実は、この『雇用保険二事業の保険料』の一部が助成金の原資になっているのです。
ですから、雇用保険の適用を受けている企業には、当然、助成金を獲得する権利があります。
しかし、活用している企業と、活用出来てない企業がある。
とても不公平な事だとは、思いませんか。
助成金は、消費税対象外の雑収入。
使途も自由な純益です。
適正な手続きで上手に活用する事をお勧めします。
1.キャリアアップ助成金
短時間労働者労働時間延長支援コース

≪概 要≫
『年収106万円の壁』
『年収130万円の壁』
最近、よく耳にする言葉では、ありませんか。
一方、『少子化の進行による人手不足』・・・これに追い打ちをかける『年収の壁問題』
これを解決するため、新たな助成金が新設されました。
労働者にとっては、
「年収の壁」を意識せず働き、社会保険に加入することで、処遇改善につながる!
事業主の皆さまにおいては、人手不足解消のテコとして!
キャリアアップ助成金
『短時間労働者労働時間延長支援コース』が新設されました。
短時間労働者の労働時間を延長し、新たに社会保険に加入させるとともに、
収入増加の取り組みを行った事業主に、ひとり最大75万円が助成されます。
≪1年目の取組≫
| 要件 | ひとり当たりの助成額 | |||
| 週所定労働時間の延長 | 賃金の増額 | 小規模企業 | 中小企業 | 大企業 |
| 5時間以上 | ー | 50万円 | 40万円 | 30万円 |
| 4時間以上5時間未満 | 5%以上 | |||
| 3時間以上4時間未満 | 10%以上 | |||
| 2時間以上3時間未満 | 15%以上 | |||
≪2年目の取組≫
| 要件 | ひとり当たりの助成額 | |||
| 週所定労働時間 の延長 | 賃金の増額 | 小規模企業 | 中小企業 | 大企業 |
| 労働時間を更に 2時間以上延長 | ー | 25万円 | 20万円 | 15万円 |
| ー | ||||
| ー | 基本給を更に5%以上増加 又は昇給・賞与もしくは退職金 制度の適用 | |||
※小規模企業とは、常時雇用する労働者の数が30人以下である事業主を指します。
対象となる労働者は、社会保険の加入日の6か月前の日以前から継続して雇用 され、
社会保険の加入要件を満たさない条件で就業していた者になります。
従来の制度に見られた、
助成金を受給するためには、事業主にも応分の負担を求める、と言ったこともなく。
ひとり当たり75万円。
かつ人数制限なしと言うことですから、
なんとも魅力的な助成金では、ないでしょうか。
但し、この助成金には、事業主も従業員さんも越えなければならない壁があります。
それは、長年固定観念化された『130万円の壁』問題です。
固定観念にとらわれず、時代の流れを理解して、
事業主も従業員さんも乗り越えなければなりません。
政府は、2030年までに最低賃金を全国平均1500円とする方針です。
何と、最低賃金を1500円とすることは、多くの野党も賛成しています。
2030年までに最低賃金を全国平均1500円にするためには、
最低賃金を毎年平均74円上げていくことが必要です。
事業主は、
社会保険料の負担をしても、人手不足の緩和につながり大きなメリットがあること。
新たに新人を採用するには、大金が掛かること。
今いる人が働く時間を延ばしてくれるのが、会社にとって大きなプラスになること。
130万円以内で働いてもらえる時間は、最低賃金の上昇と共に急速に短くなること。
従業員さんにとっては、
130万円の壁を越えて働く人との収入格差が、みるみる大きくなって行くこと。
時間当たりの賃金が上昇していく中で、働く時間に制限を設けることは、大きな損に繋がること。
これらを、理解して貰わなければなりません。
最低賃金が急激に上昇し、社会保険の加入条件も拡大される時代です。
いちど、しっかりと検討されることをお勧めします。
2.キャリアアップ助成金・正社員化コース
有期・無期の非正規従業員を正社員に転換させることで助成されます。
≪助成額≫
| 対象者 | 企業規模 | 有期雇用労働者 | 無期雇用労働者 |
| 重点支援 対象者 | 中小企業 | 80万円(40万円×2期) | 40万円(20万円×2期) |
| 大企業 | 60万円(30万円×2期) | 30万円(15万円×2期) | |
| 上記以外 | 中小企業 | 40万円×1期 | 20万円×1期 |
| 大企業 | 30万円×1期 | 15万円×1期 |
令和7年度から「重点支援対象者」が設けられ、助成額が変わりました。
≪重点支援対象者とは、以下の1.2.3.該当者です。≫
1.雇入れから3年以上経過している有期雇用労働者
2.雇入れから3年未満で、以下のいずれにも該当する有期雇用労働者
①過去5年間で正規雇用だった期間が1年以下
②過去1年間に正規雇用で雇用されていない
3.派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者
◆加算額:1事業所当たり1回の加算額
| 措置内容 | 加算額 |
| 正社員転換制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換 | 20万円(大企業15万円) |
| 多様な正社員制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換 | 40万円(大企業30万円) |
※正社員に転換した場合は、転換前6カ月と転換後6カ月を比較して
1時間当たりの賃金が3%以上上昇していることが必要です。
≪令和7年度からの新規学卒者の取扱いについて≫
対象労働者が新規学卒者に該当し、
申請事業主に雇い入れられた日から起算 して
1年を経過していない者については、支給対象外となります。
新規学卒者とは、
新たに学校を卒業しようとする者および卒業年度の3月31日までに内定を得た者を言います。
令和7年4月1日に雇用された新規学卒者に付いては、令和8年3月31日まで支給対象外です。
一方、3月15日に卒業式を迎えたが就職先が決まっておらず
4月2日以降に就職先が決まり、 5月に就職したという者については、支給対象となり得ます。

≪概 要≫
労働者の雇用契約の形態は、
(1)正規雇用従業員(正社員)
(2)非正規雇用従業員(パート社員等)
に大別されます。
政府は、従業員にとって雇用の安定度が高い正社員を増やすことを目指しています。
そこで、労働者の雇用の安定を計る事業主には、ご褒美を出すことにしています。
ちなみに
正社員には、『勤務地限定正社員』『職務限定正社員』『短時間正社員』を含みます。
さて、この助成金に於ける正社員、
助成金の対象になる労働者には定義があり、
助成金の対象になる正社員の要件は、
同一の事業所内の正規雇用労働者に適用される就業規則が適用されている労働者
かつ、
「賞与または退職金の制度」および「昇給」が適用されている者に限る
となっています。
また、
助成金の対象になる労働者の要件は、
賃金の額または計算方法が「正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等」の適用 を
6か月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者となっています。
上記の助成額は、対象者一人当たりの金額です。
3人出ればその3倍、5人出ればその5倍の助成金に繋がります。
また、1年度1事業所当たり20人まで可能です。
年度毎に、事業所毎に最大20人と言うのが、大きな助成金に繋がります。
ちなみに当所の場合、この助成金だけで累計数百万円という顧問先が何社もあります。
3.キャリアアップ助成金・障害者正社員化コース
障害のある労働者を正社員に転換させた場合に助成されます。
≪助成額≫
| 支給対象者 | 措置内容 | 支給総額 | 支給対象 期間 | 各支給対象期に於ける支給額 |
| 重度身体障害者 重度知的障害者 及び精神障害者 | 有期雇用から 正規雇用転換 | 120万円 (90万円) | 1年 | 60万円×2期 (45万円×2期) |
| 有期雇用から 無期雇用転換 | 60万円 (45万円) | 30万円×2期 (22.5万円×2期) | ||
| 無期雇用から 正規雇用転換 | 60万円 (45万円) | 30万円×2期 (22.5万円×2期) | ||
| 重度以外の身体障害者 知的障害者、 発達障害者、 難病患者、 高次脳機能障害者 | 有期雇用から 正規雇用転換 | 90万円 (67.5万円) | 45万円×2期 33.5万円×2期 ※第2期は34万円 | |
| 有期雇用から 無期雇用転換 | 45万円 (33万円) | 22.5万円×2期 (16.5万円×2期) | ||
| 無期雇用から 正規雇用転換 | 45万円 (33万円) | 22.5万円×2期 (16.5万円×2期) |
※キャリアアップ助成金における正社員化コースの支給申請上限人数には該当しません。
※上記の額は、対象労働者ひとり当たりの額です。
≪概 要≫
近年、障害者雇用は、増大しています。
そして、生産者年齢の労働者が減少している現在、
障害者の社会進出は、喫緊の課題です。
キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)は、
障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るために、
次の①または②のいずれ かに該当する措置を継続的に講じた場合に助成します。
① 障害のある有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含みます)
または無期雇用労働者に転換すること
② 障害のある無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換すること
≪対象となる労働者≫
●転換を行った日の時点で、
次のいずれかに該当する労働者であること。
(1)身体障害者 (2)知的障害者 (3)精神障害者
(4)発達障害者 (5)難病患者
(6)脳の機能的損傷に基づく精神障害である高次脳機能障害であると診断された者
●就労継続支援A型事業における利用者でないこと。
●支給対象事業主に、賃金の額又は計算方法が正規雇用労働者と異なる雇用区分の
就業規則等の適用を通算6か月以上受けて雇用される有期・無期雇用労働者であること

≪正社員定義≫
同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が
適用されている労働者
「賞与または退職金の制度」および「昇給」が適用されている者に限ります
≪対象となる労働者の要件≫
賃金の額または計算方法が
「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月 以上受けて
雇用されている有期または無期雇用労働者
4.働き方改革推進支援助成金
勤務間インターバル導入コース
当日の業務の終了時間から翌日の業務の開始時間までの休息時間を
一定以上に引上げる制度を導入することで助成されます。
≪助成上限額≫
| 休息時間数 | 「新規導入」に該当する取組がある場合 | 新規導入」に該当する取組がなく、 「適用範囲の拡大」又は 「時間延長」に該当する取組がある場合 |
| 9時間以上 11時間未満 | 100万円 | 50万円 |
| 11時間以上 | 120万円 | 60万円 |
業務の効率化の為の取組の実施に要した経費の一部を、
成果目標の達成状況に応じて支給します。
※対象経費の合計額に補助率3/4を乗じた額を助成します。
ただし上の表の上限額を超える場合は、上限額とします

≪概 要≫
「勤務間インターバル制度」とは、
前日の勤務終了後、翌日の勤務までに
一定時間以上の「休息時間」を設けることで、
働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、
健康保持や過重労働の防止を図ろうとするものです。
その為には、就業規則に勤務間インターバルに関する規定を設け、
業務の効率化など労働時間の短縮を図る取り組みが必要です。
この助成金は、そうした取り組みに係る経費の一部を助成するものです。
「成果目標」の達成を目指して実施してください。
事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、
休息時間数が「9時間以上11時間未満」
または「11時間以上」の勤務間インターバルを導入し、
就業規則に定めて定着を図ること。
人材の確保、業務の効率化、生産性の向上は、多くの企業の課題です。
取り組んでみられては如何でしょうか。
上記の勤務間インターバル制度を導入するために必要な、
以下の取組費用を助成します。
1.労務管理担当者に対する研修
2.労働者に対する研修、周知・啓発
3.外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
4.就業規則・労使協定等の作成・変更
5.人材確保に向けた取組
6.労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7.労務管理用機器の導入・更新
8.デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9.労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※研修には、業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
尚、
常時使用する労働者数が30名以下かつ支給対象の取組の6、7を実施する場合で
その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5となります。
又、
賃金額の引上げを成果目標に加えた場合の加算額は、
指定した労働者の賃金引上げ数の合計に応じて、
次の表のとおり、上記上限額に加算されます。
なお、引き上げ人数は30人を上限とするとなっています。
上記上限額に加算
<常時使用する労働者の数が30人以下の場合>
| 引き上げ人数 | 1~3人 | 4~6人 | 7~10人 | 11人~30人 |
| 3%以上引上げ | 12万円 | 24万円 | 40万円 | 1人当たり4万円 (上限120万円) |
| 5%以上引上げ | 48万円 | 96万円 | 160万円 | 1人当たり16万円 (上限480万円) |
| 7%以上引上げ | 72万円 | 144万円 | 240万円 | 一人当たり24万円 (上限720万円) |
<常時使用する労働者の数が30人超の場合>
| 引き上げ人数 | 1~3人 | 4~6人 | 7~10人 | 11人~30人 |
| 3%以上引上げ | 6万円 | 12万円 | 20万円 | 1人当たり5万円 (上限150万円) |
| 5%以上引上げ | 24万円 | 48万円 | 80万円 | 1人当たり8万円 (上限240万円) |
| 7%以上引上げ | 36万円 | 72万円 | 120万円 | 一人当たり12万円 (上限360万円) |
【対象事業主】・・・以下のいずれにも該当する事業主です。
1.労働者災害補償保険の適用を受ける中小 企業事業主であること。
2.36協定を締結しており、原則として、
過 去2年間において月45時間を超える時間外労働の実態があること。
3.年5日の年次有給休暇の取得に向けて 就業規則等を整備していること。
4.以下のいずれかに該当する事業場を有す ること。
① 勤務間インターバルを導入していない事業場
② 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インタ ーバルを導入している事業場であって、
対象と なる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
③ 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インタ ーバルを導入している事業場
【締め切り】
申請の受付は、2025年11月28日(金)まで必着です。
(給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、11月28日以前に受付を締め切る場合があります。)
5.特定求職者雇用開発助成金・特定就職困難者コース
60歳以上の高齢者や母子家庭の母等の雇用に助成されます。
≪助成額≫
短時間労働者以外の者の場合
| 対象労働者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
| 60歳以上高年齢者 母子家庭の母等 | 60(50)万円 | 1年 | 30万円 × 2期 ( 25万円 × 2期 ) |
| 身体・知的障害者 | 120(50)万円 | 2年 (1年) | 30万円 × 4期 ( 25万円 × 2期 ) |
| 重度障害者等 重度障害者 45 歳以上の障害者 精神障害者 | 240(100)万円 | 3年 (1年6か月) | 40万円 × 6期 ( 33万円※× 3期 ) ※第3期の支給額は34万円 |
短時間労働者の場合
| 対象労働者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
| 60歳以上高年齢者 母子家庭の母等 | 40(30)万円 | 1年 | 20万円 × 2期 ( 15万円 × 2期 ) |
| 重度障碍者を含む 身体・知的・ 精神障害者 | 80(30)万円 | 2年 (1年) | 20万円 × 4期 ( 15万円 × 2期 ) |
※対象労働者に支払われた賃金の一部に相当する額として、
上表の金額が、 支給対象期(6か月)ごとに支給されます。
※( )内は中小企業以外の企業に対する支給額・助成対象期間です。
※ ハローワーク、地方運輸局、雇用関係給付金の取扱に係る同意書を労働局に提出している
特定地方公共団体、 有料・無料職業紹介事業者または無料船員職業紹介事業者の
斡旋による採用でないと対象になりません。

≪概 要≫
高年齢者、障害者、母子家庭の母等の就職困難者を、
ハローワーク等 の紹 介により、
継続して雇用する労働者として雇い入 れる事業主に
助成金が支給されます。
この助成金は、ハローワークが管理対応してくれる数少ない助成金のひとつです。
上記の様なハンデを持った労働者を雇用し雇用保険に加入させると
3ヵ月前後で『助成金のお知らせ』が届きます。
これによって、事業主は採用した労働者が助成金の対象者であることを知ります。
採用から5ヵ月前後経過すると
『助成金の受給の手引き』と『受給申請書』が届きます。
手引きに従って、受給申請書を作成し労働局に提出すると受給の準備が完了します。
6.両立支援等助成金・ 育児休業等支援コース
育児休業の取得時と職場復帰時に助成されます。
≪助成額≫
| 助成の段階 | 支給額 | |
| 育休取得時・職場復帰時 | A 休業取得時 | 30万円 |
| B 職場復帰時 | 30万円 | |

≪概 要≫
少子化問題の最大の課題は、女性の出生率向上です。
政府は、女性の出産。子育て。に付いては、
手厚い対策を施しています。
出産・子育ては、これまで以上に重要なテーマ
この機会に、御社も福利厚生を充実させ、
他社との差別化を図っては、如何でしょうか。
「育休復帰支援プラン 」 を作成し 、
プランに沿って労働者の円滑な育児休業の取得 ・職場復帰に取り組み 、
育児休業を取得した労働者が生じた 中小企業事業主 に支給されます 。
≪主な要件≫
A:育休取得時
●育児休業の取得、職場復帰についてプランにより支援する措置を実施する旨を、
あらかじめ労働者へ周知 すること。
●育児に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で
育児の状況や今後の働き方についての希望等を確認のうえ、プランを作成 すること。
●プランに基づき、
対象労働者の育児休業(産前休業から引き続き産後休業及び育児休業をする場合は、
産前休業。)の開始日の前日までに、プランに基づいて業務の引き継ぎを実施し、
対象労働者に、
連続3か月以上の育児休業 (産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は、
産後休業を含んで連続3か月以上)を取得させること。
B:職場復帰時
●対象労働者の育児休業中にプランに基づ く措置を実施し 、
職務や業務 の情報・資料の提供 を実施すること。
●育休取得時にかかる同一の対象労働者に対し、
育児休業終了前にその上司または人事労務担当者が 面談を実施 し、
面談結果を記録すること。
●対象労働者を、面談結果を踏まえ原則として原職等に復帰 させ 、
原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険者として6か月以上継続雇用していること。
7.両立支援等助成金・育休中等代替支援コース
育児休業者等の業務の代替や新規雇用に助成されます。
≪助成額≫
| 支給額 (育児休業取得者/制度利用者1名あたり) | ||
| [1]手当支給等 (育児休業) | 1.業務体制整備経費:6万円(育児休業期間1カ月未満は2万円) ※労務コンサルを外部の専門家に委託:20万円 | |
| 2.業務代替手当:業務代替者に支給した手当総額の3/4 ※上限:10万円/月 | ||
| [2]手当支給等 (短時間勤務) | 1.業務体制整備経費:3万円(子が3歳になるまでの期間・支給申請1年毎) ※労務コンサルを外部の専門家に委託:20万円 | |
| 2.業務代替手当:業務代替者に支給した手当総額の3/4 ※上限:3万円/月 | ||
| [3]新規雇用 (育児休業) 中小企業のみ | 育休中代替した期間 | 支給額 |
| 7日以上14日未満 | 9万円 | |
| 14日以上1カ月未満 | 13.5万円 | |
| 1カ月以上3ヵ月未満 | 27万円 | |
| 3ヵ月以上6ヵ月未満 | 45万円 | |
| 6ヵ月以上 | 67.5万円 |
※1事業主1年度当たり[1][2][3]合わせて10名まで初回対象者が出てから5年間
※プラチナくるみん認定事業主は、別途加算あり
※有期雇用労働者加算:10万円
※育児休業等に関する情報公開加算:2万円

≪概 要≫
育児休業取得者や育児のための短時間勤務制度利用者の
業務を代替する周囲の労働者への手当支給等の取組や、
育児休業取得者の代替要員の新規雇用を行った場合に
助成するものです。
本コースでは、以下の3つの場合に助成金が支給されます。
[1]手当支給等(育児休業)
:育児休業取得者の業務を代替する周囲の労働者に対して、手当支給等の取組を行った場合
[2]手当支給等(短時間勤務)
:育児のための短時間勤務制度を利用する労働者の業務を代替する
周囲の労働者に対し、手当支給等の取組を行った場合
[3]新規雇用(育児休業)
:育児休業取得者の業務を代替する労働者を新規雇用(派遣受入れ含む)により確保した場合
≪[1]手当支給等(育児休業)の主な支給要件≫
①対象労働者(育児休業取得者)の業務を、事業主が雇用する労働者(業務代替者)に代替させた。
②業務の見直し・効率化のための取組を実施している。
③代替業務に対応した賃金制度を労働協約または就業規則に定め、
制度に基づき業務代替期間における業務代替者の賃金を増額させている。
④対象労働者に7日以上の育児休業を取得させた。
⑤育児休業制度などを労働協約または就業規則に定めている。
⑥次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ている。
※②、③は、業務代替期間の開始日までに、
⑤は、対象労働者の育児休業開始日の前日までに実施する必要があります。
対象労働者の育児休業期間が1カ月以上の場合は、さらに下記の取組が必要です。
⑦育児休業取得者を現職等に復帰させる旨を労働協約または就業規則に定めている。
⑧育児休業終了後、対象労働者を原則として原職等に復帰させたこと。
⑨対象労働者を原職等に復帰した日から支給申請日までの3カ月以上継続した期間に付いて、
雇用保険被保険者として雇用していること。
※⑦は、対象労働者の職場復帰までに実施することが必要です。
≪[2]手当支給等(短時間勤務)の主な支給要件≫
①3歳未満の子を養育する労働者が、育児のための短時間勤務制度を1カ月以上利用したこと。
②育児のための短時間勤務制度利用者の業務を
事業主が雇用する労働者(業務代替者)に代替させていること。
③業務の見直し・効率化のための取組を実施している。
④代替業務に対応した賃金制度を労働協約または就業規則に定め、
制度に基づき業務代替期間における業務代替者の賃金を増額させている。
⑤対象制度利用者を、短時間勤務制度の利用開始日
および支給申請日に於いて、雇用保険被保険者として雇用していること。
⑥育児のための短時間勤務制度などを労働協約または就業規則に定めている。
⑦次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ている。
※③、④は、業務代替期間の開始日までに、
⑥は、対象制度利用者の短時間勤務制度の開始日の前日までに
実施する必要があります。
≪[3]手当支給等(育児休業)の主な支給要件≫
①対象労働者(育児休業取得者)の代替要員を新たな雇入れまたは新たな派遣受入れにより確保した。
②対象労働者に7日以上の育児休業を取得させた。
③対象育児休業者を育児休業の開始日及び職場復帰後、支給申請日までの間に於いて、
雇用保険被保険者として雇用していたこと。
④育児休業制度などを労働協約または就業規則に定めている。
⑤次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働協に届けている。
※④は、対象育児休業取得者の育児休業開始日の前日までに実施が必要。
対象労働者の育児休業期間が1カ月以上の場合は、さらに下記の取組が必要です。
⑥育児休業取得者を原職等に復帰させる旨を労働協約または就業規則に定めている。
⑦育児休業終了後、対象労働者を原則として原職等に復帰させた。
⑧対象労働者を原職等に復帰した日から支給申請日までの3ヵ月以上継続した期間に付いて、
雇用保険被保険者として雇用している。
8.業務改善助成金・通常コース
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引上げ、
生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その費用の一部を助成する制度です。
≪助成上限額≫
| コース 区分 | 事業場内 最低賃金の 引上げ額 | 引上げる 労働者数 | 助成金上限額 | |
| 右記以外 の事業者 | 事業場規模 30人未満の 事業場 | |||
| 30円 コース | 30円以上 | 1人 | 30万円 | 60万円 |
| 2~3人 | 50万円 | 90万円 | ||
| 4~6人 | 70万円 | 100万円 | ||
| 7人以上 | 100万円 | 120万円 | ||
| 10人以上 | 120万円 | 130万円 | ||
| 45円 コース | 45円以上 | 1人 | 45万円 | 80万円 |
| 2~3人 | 70万円 | 110万円 | ||
| 4~6人 | 100万円 | 140万円 | ||
| 7人以上 | 150万円 | 160万円 | ||
| 10人以上 | 180万円 | 180万円 | ||
| 60円 コース | 60円以上 | 1人 | 60万円 | 110万円 |
| 2~3人 | 90万円 | 160万円 | ||
| 4~6人 | 150万円 | 190万円 | ||
| 7人以上 | 230万円 | 230万円 | ||
| 10人以上 | 300万円 | 300万円 | ||
| 90円 コース | 90円以上 | 1人 | 90万円 | 170万円 |
| 2~3人 | 150万円 | 240万円 | ||
| 4~6人 | 270万円 | 290万円 | ||
| 7人以上 | 450万円 | 450万円 | ||
| 10人以上 | 600万円 | 600万円 | ||
助成される金額は、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用に
一定の助成率を掛けた金額と助成上限額を比較し、いずれか安い方の金額です。
≪助成率≫
| 事業場内最低賃金 1,000円未満 | 4/5 | 事業場内最低賃金 1,000円以上 | 3/4 |
≪引上げ対象労働者とは≫
▶ 事業場内最低賃金である労働者
▶ 事業場内最低賃金である労働者の賃金を引き上げることにより、
賃金額が追い抜かれる労働者 が「引き上げる労働者」に算入されます。
(ただし、いずれも申請コースと同額以上賃金を引き上げる必要があります。)
≪特例事業場とは≫
以下の要件に当てはまる場合が特例事業者と なります。
なお、②に該当する場合は、助成対象経費の拡充も受けられます。
①賃金要件:事業場内最低賃金1,000円未満の事業場
②物価高騰等要件:原材料費の高騰など社会的・経済的環 境の変化等の外的要因により、
申請前 3か月間のうち任意の1か月の利益率 が前年同月に比べ
3%ポイント(%で表された2つの数値の差)以上 低下している事業者
※物価高騰等要件に該当する事業者は、一定の 自動車の導入やパソコン等の
新規導入が認め られる場合がございます。

≪概 要≫
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の
生産性向上を支援し、
事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の
引上げを図るための制度です。
最低賃金を引き上げる為には、業務の効率化、生産性の向上は不可欠です。
そこで、
生産性向上のための設備投資等を行い、
事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、
その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。
≪助成額≫
申請コースごとに定める引上げ額以上、事業場内最低賃金を引き上げた場合、
生産性向上のための設備投資等にかかった費用に
助成率を乗じて算出した額を助成します。
なお、申請コースごとに、
助成対象事業場、引上げ額、助成率、引き上げる労働者数、
助成の上限額が定められていますので、ご注意ください。
≪支給の要件≫
1.賃金引上計画を策定すること
事業場内最低賃金を一定額以上引上げることを就業規則等に規定する
2.引上げ後の賃金を支払うこと
3.生産性向上に資する機器・設備やコンサルティングの導入、
人材育成・教育訓練を実施することにより業務改善を行い
その費用を支払うこと
4.解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など
≪活用事例≫
1.POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
2.リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
3.顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化 など
9.65歳超雇用推進助成金:高年齢者無期雇用転換コース
50歳以上の有期契約労働者を無期雇用に転換した場合に助成されます。
≪助成額≫
| 中小企業 | 中小企業以外 | |
|---|---|---|
| 1人当たり助成額 | 30万円 | 23万円 |
1適用事業所当たり1年度に10人まで可

≪支給対象労働者≫
支給対象労働者とは、
以下のすべてに該当する者を言う。
①50歳以上で、定年年齢未満の有期契約労働者であること。
②支給対象事業主に雇用される期間が転換日において通算して6か月以上5年以内であること。
③無期雇用転換後に65歳以上まで雇用される見込みがあること。
※同種の業務に従事する期間の定めのない 労働契約を締結する労働者に適用される定年年齢が
65歳を超える場合においては当該年齢
④転換日に於いて64歳以上でないこと。
⑤派遣労働者でないことが必要です。
尚、この助成金を受給するには、『無期雇用転換計画書』を提出する前に
『高齢者雇用管理に関する措置』として、以下の中から一つ以上の実施が必要です。
1.職業の能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
2.作業施設・方法の改善
3.健康管理・安全衛生の配慮
4.職域の拡大
5.知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
6.賃金体系の見直し
7.勤務時間制度の弾力化
≪主な受給要件≫
(1)「無期雇用転換計画書」を(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出し、
計画の認定 を受けていること。
(2)有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を労働協約または就業規則
その他これに準ず るものに規定していること。
但し、実施時期が明示され、かつ有期契約労働者として平成25年4月1日以降に
締結された契約に係る期間が通算5年 以内の者を無期雇用労働者に転換するものに
限ります。
(3)上記の制度の規定に基づき、雇用する50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を
無期雇用労働者に転換すること。
但し、 無期雇用転換日において64歳以上の者はこの助成金の対象労働者になりません。
(4)上記により転換された労働者を、転換後6カ月以上の期間継続して雇用し、
当該労働者に 対して転換後6カ月分の賃金を支給すること。
但し、勤務をした日数が11日未満の月は除きます。
(5)無期雇用転換計画書提出日の前日から支給申請日の前日までの間に、
高年齢者雇用安定法第8条 または第9条第1項の規定と異なる定めをしていないこと。
また、高年齢者雇用確保措置を講じていないことにより、同法第10条第2項に基づき、
当該雇 用確保措置を講ずべきことの勧告を受けていないこと及び、法令に基づいた
適切な高年齢者就業 確保措置を講じていないことにより、同法第10条の3第2項に
基づき当該就業確保措置の是正に向けた計画作成勧告を受けていない事業主であること
10.65歳超雇用推進助成金:65歳超継続雇用促進コース
≪概 要≫
65歳以上への定年引上げ等の取組みを実施した
事業主に対して助成するものであり、
高年齢者の就労機会の確保及び希望者全員が安心して働ける
雇用基盤の整備を目的としています。
≪助成額≫
【 定年の引上げ、又は、定年の定めの廃止】
(注)旧定年年齢が70歳未満のものに限ること
| 措置内容 対象被保険者数 | 65歳へ 引上げ | 66歳から69歳に引上 | 70歳 以上引上 | 定年廃止 | |
| 5歳未満 | 5歳以上 | ||||
| 1~3人 | 15万円 | 20万円 | 30万円 | 30万円 | 40万 |
| 4~6人 | 20万円 | 25万円 | 50万円 | 50万円 | 80万円 |
| 7~9人 | 25万円 | 30万円 | 85万円 | 85万円 | 120万円 |
| 10人以上 | 30万円 | 35万円 | 105万円 | 105万円 | 160万円 |
【 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入 】
(注)旧定年年齢及び継続雇用年齢が70歳未満のものに限ること
| 措置内容 対象被保険者数 | 66歳から69歳に引上 | 70歳以上へ引上 |
| 1~3人 | 15万円 | 30万円 |
| 4~6人 | 25万円 | 50万円 |
| 7~9人 | 40万円 | 80万円 |
| 10人以上 | 60万円 | 100万円 |

定年年齢引上げ等の措置の実施日が属する月の 翌月から起算して
4か月以内の各月月初から15日までに、
支給申請して下さい。
「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)支給申請書」に必要な書類を添えて、
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の各都道府県支部高齢・障害者業務課に申請する。
なお、各月ごとの予算額上限もしくは四半期ごとの予算額上限の超過が予見される場合、
または、各月の申請受付件数の動向から、各月の予算額上限を超える恐れが高いと認める場合、
支給申請の受付を停止する場合があります。
≪対象被保険者とは、以下の①②に該当するもの≫
①雇用保険被保険者
・支給申請日の前日において、
当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者
・定年前の無期雇用者である短時間就労者
・福祉施設の利用者で雇用関係のあるもの
・法人の役員等で兼務役員雇用実態証明書を提出しているもの
・個人事業主と同居の親族で同居親族雇用実態証明書を提出しているもの
②就業規則の適用者:申請日前日において次のすべてに当てはまる者
・定年前の無期雇用者又は無期雇用契約の定年後に希望者全員継続雇用制度
もしくは会社選別継続雇用制度により引き続き雇用 されている者
・改正前、改正後の就業規則の適用者
・定年の引上げ等の制度を規定した就業規則等の対象職種の者
≪対象労働者とは、ならないもの≫
① 支給申請日前日において雇用期間が1年に満たない者
② 60歳未満の者
③ 改正前、改正後の就業規則を適用していない定年前の無期雇用者、定年後の継続 雇用者
④ 賃金台帳により在籍確認ができない者(休職者等)
⑤ 改正前就業規則に規定していた定年年齢以上の年齢で、個別の雇用契約により雇用された者
⑥ 改正前就業規則に規定される定年年齢以上の年齢で、有期から無期雇用者に転換された者
⑦ 就業規則等に規定された制度を適用せず、個別対応により雇用している者
⑧ 改正前就業規則に規 定された定年年齢、継続雇用年齢以上の年齢まで継続雇用している者
⑨ 改正前就業規則において、有期契約と定義されている者
⑩ 定年を引上げた職種等区分に該当しない者
⑪ 定年引上げ等の制度の対象とならない者
≪主な受給要件≫
1. 労働協約または就業規則により次の(イ)~(ハ)までのいずれかに該当する
新しい制度を実施し、就業規則を労働基準監督署へ届出た事業主であること。
- (イ)旧定年年齢を上回る65歳以上への定年引上げ
- (ロ)定年の定めの廃止
- (ハ)旧定年年齢及び継続雇用年齢を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入
- (ニ)他社による継続雇用制度の導入
2. 就業規則により定年の引上げ等を実施する場合は
専門家等に就業規則の作成又は相談・指導を委託し経費を支出したこと。
または労働協約により定年の引上げ等の制度を締結するためコンサルタントに相談し
経費を支出したこと。
3. 高年齢者雇用推進者の選任及び次の(a)から(g)までの
高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施している事業主であること。
【高年齢者雇用管理に関する措置】
(a)職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
(b)作業施設・方法の改善
(c)健康管理、安全衛生の配慮
(d)職域の拡大
(e)知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
(f)賃金体系の見直し
(g)勤務時間制度の弾力化

雇用に関する助成金
ぜひとも、活用したいですね。