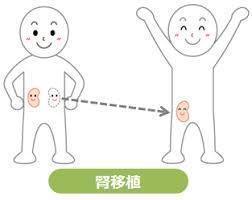労働トラブル対策集

インターネットの普及と労働者の権利意識の高揚で、
かつては考えられなかった要求をする従業員が増えました。
しかしながら会社をおびやかす労働トラブルの多くは
就業規則の規定内容を工夫する事で
会社のダメージを最小化する事が出来ます。
ここでは、社員トラブルのさまざまな事例を紹介しながら、その対処例を掲載しました。
試用期間中の解雇

社員を中途採用したところ、
営業成績が思わしくないため
解雇することにしました。
ところが本人に解雇を言い渡すと
「自分なりに精一杯働いた。試用期間中と言っても、これは不当解雇だ」と
いって聞きません。
労働基準監督署に訴えるともいっています。
●試用期間中の解雇とは?
試用期間中は、社員の適格性を判断する期間です。
ですから「会社が不適格と認めた者を解雇する」のは止むおえない事です。
但し、現実に解雇が認められるかというと、これは非常に微妙です。
勿論、本採用以降の解雇に比べれば、解雇のハードルが低いと言われていますが、
社員を解雇するためには、
「客観的にみて合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められる。」
必要があるからです。
試用期間中といえども社員であることに変わりはないので、
客観的・社会的な見地に立った、判断が必要となってきます。
●能力不足は解雇の理由にならない
「能力不足」というのは、解雇理由で最も多い項目の一つなのですが、
裁判で争ったときは、90%会社側が負けます。
と言うのは、
裁判に於いて能力不足は、会社の教育・指導にも責任があると、判断されるのです。
そして、社員に一方的な責任を負わせるような措置(解雇)を認めないからです。
単に試用期間中だけの実績をみて「営業成績不振」「能力不足」と判断し、
解雇するのは難しいと言えます。
それでは、どのようなときに解雇が認められるのでしょうか。
特定能力を必要とすることを条件に募集し、その者が、能力を有しないと判断された場合や、
上司にきわめて反抗的だったり、
服務規律違反、欠勤が多い場合などは、解雇が認められ易くなります。
会社の秩序を乱し、悪い空気を社内に流すような社員は、
本採用しても会社にマイナスを与えるだけですので、
客観的に合理的な理由があるときは、毅然たる態度でのぞむべきではないでしょうか。
●トラブル防止には就業規則に規定が必要
本来、労働契約を締結するか取り消すかは、会社と社員が話し合って決めることです。
試用期間中に解雇したとしても、社員が納得して辞めるのであれば、
何のトラブルも発生しません。
社員の納得を得る為には、就業規則で試用期間中の解雇事由を定めておくことです。
そのうえで労働契約を結ぶときに、
どのような場合に本採用が拒否されるのかを説明しておくことが大切です。
このような過程を踏むことで、解雇トラブルの可能性が減るだけでなく、
裁判でも、会社側に有利な材料が残ることになります。
試用期間中の社員が一ヶ月も休業
従業員を雇い入れたのですが、入社後すぐに病気療養という理由から、
1カ月近くも休まれてしまいました。
3ヶ月の試用期間は、すでに過ぎたのですが、
本人の能力がまだつかみきれず、本採用していいか悩んでいます。
●試用期間とは
試用期間とは、会社が社員の勤務態度や能力、人間性などを確認し、
本採用するかどうかを、判断する為の期間です。
しかしこの事例のように、社員の適格性の判断が十分に行えない場合があります。
このようなときは、就業規則の規定をもとに「試用期間を延長」することができます。
●試用期間の延長と就業規則
試用期間は、原則として入社時に社員に言い渡した期間でなければなりません。
しかし、就業規則に「試用期間の延長」についての記載があれば、
延長することが可能になります。
ただし、就業規則に記載があったとしても、会社の都合だけで延長することはできません。
この事例のように「本人の長期休暇により十分に判断時間がえられなかった」など、
合理的な理由があった場合のみ認められる事になります。
いずれにせよ試用期間に付いては、延長・短縮の規定を就業規則に盛り込んで置く事が
重要になります。
休職を繰り返す従業員に困惑

社員が3カ月の病気療養から戻ってきたと思ったら、
また同じ病気で休職してしまいました。
その後、回復して復職しましたが病欠が多く
会社運営にも影響が出ています。
何とかならないでしょうか?
●休職者にどう対応するのか
日本の法律は、「解雇」を堅く禁じており、
病欠で職場をしばらく離れていたからといって、なかなか解雇できないのが現状です。
しかし、休職を繰り返すことによって会社運営に影響が出ているのでしたら、
対策を講じないわけにはいきません。
まず社員の病気が医師の診断に基づくものかを確認してみましょう。
医師の診断書を提出させれば、休みの理由が本当に病気によるものだということが
確認できます。
次に社員とよく話し合うことです。
会社を辞めてしっかりと療養したほうがいいのか、
それとも再度休職させてきちんと治癒してから復職したほうがいいのかを話し合います。
最近は「うつ病」などを患う人も増えており、
会社が社員を精神的に追い込むと、自殺に発展することもあるので注意が必要です。
このようなときは、医師を介して話す方法もあります。
一方的に会社の意見を押し付けるのではなく、
あくまでも、どうするのが本人や会社にとって最適であるかを話しあうことが大切です。
●就業規則に休職制度を設ける
就業規則の対策としては、「休職制度」を導入することです。
休職とは、社員が社員の身分を残したまま長期休暇に入ることです。
休職については、法律に定めがないため、会社が任意でルールを決められます。
休職制度を設けるときの留意点は、
1 休職期間を何年(何か月)と具体的に規定すること
2 休職を繰り返したときは、前後の期間を通算できるようにすること
3 休職期間中も定期的に連絡が取れるようにすること
4 本人と連絡が取れない場合の対策を決めて置くこと
5 復職の条件と手続きをきめておくこと
そして、
休職期間が満了しても復職できないときは自動退職とすることなどがあげられます。
前触れもなく従業員と連絡が取れなくなった

社員の一人が突然会社に出てこなくなりました。
自宅に電話しても連絡がとれず行方がわかりません。
重大な服務規律違反として解雇したいのですが、
どのようにしたらいいでしょうか?
●行方不明者を退職させるには
社員を「解雇」するためには、法律上、少なくとも30日前の予告が必要です。
ところが、この事例のように、
社員が突然会社に出てこなくなって連絡がとれない場合、
会社がいくら予告しようとしても解雇予告することができません。
このような場合は、
社員が連絡してくるのを待って解雇予告するか、
又は裁判所の掲示板に掲示(公示送達)することで解雇予告する方法があります。
ただ、どちらも時間と手間がかかり、現実的な対処法とはいえません。
そこで就業規則に、「ある一文」を加えておくことが非常に重要になります。
就業規則の退職の項目に「無断欠勤が連続して30日以上におよんだときは退職とする」
という文言を入れるだけです。
これだけで社員が無断欠勤し行方不明になった場合、
30日後に退職扱いにすることができます。
退職金制度のある会社は、
退職金の不支給事由に「30日以上の無断欠勤者」を加えておけば、
退職金の支払いも不要になります。
遅刻癖が直らない

当社では遅刻の常習犯がいます。
毎週月曜日は、重要なミーティングがあるのですが、
その打ち合わせにも平気で遅刻してきます。
注意しても改善しないのですが、
どのように対処したらいいのでしょうか。
●社員の遅刻を減らすには?
遅刻の常習犯は、一般の社員より、能力のある社員に多いといいます。
「自分が抜けたら会社は困るだろう」という本人の過信に加え、
上司もまた辞められては困るため、多めに見ている傾向があります。
遅刻を取り締まる方法には、次のような方法があります
1.遅刻した分の賃金をカットする。
賃金は、ノーワークノーペイが原則です。
働いていない時間の賃金は、カットすることができます。
ただし、この場合、遅刻の常習犯だけでなく、
社員全員について遅刻した場合は、賃金をカットしなければなりません。
2.就業規則の懲戒処分として賃金を減給する。
遅刻は、社員の勤務態度不良にあたりますから、減給制裁を行うことができます。
ただし、減給するためには就業規則に減給についての記載があることが必要です。
また減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額、
総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならないことになっています。
何度か注意・指導しても遅刻が改善されないときは、
減給制裁を検討してみるのもいいでしょう。
3.遅刻が改善しないようなら懲戒解雇する。
悪質な遅刻に対しては、懲戒解雇も可能です。
遅刻によって業務に大きな影響を受け、繰り返し注意するも改善されない場合です。
この場合、会社が何度も注意・指導したことを証明できるよう、遅刻のたびに始末書をとり、
それでも改善しない場合は、「今度、遅刻をしたら解雇する」と予告し、
改善しなければ解雇します。
4.皆勤手当を設ける
皆勤手当を1万円と決めておき、遅刻するたびに皆勤手当が減るようにします。
当事務所の顧問企業の中には、
この皆勤手当を2万円と高額にし、3回遅刻したらすべてなくなるとしたところ、
社員の遅刻が一気に減ったというところもあります。
また遅刻を取り締まるためには、就業規則に、きちんとルールを示しておくことが必要です。
残業をしない従業員に手を焼いている

残業をかたくなに拒否する社員がいます。
納期がせまって忙しい日も
何かと理由をつけて帰ってしまうので、
その負担が他の社員にまわってしまっています。
残業を拒否する社員に時間外労働を強制することは、出来ないのでしょうか。
●会社が残業を命ずる為には、
会社が従業員に残業をさせる為には、
「時間外労働・休日労働に関わる協定書(36協定)」を
労働基準監督署長に届出なければなりません。
しかし、この届出をしたからといって、
直ちに労働者に残業を強いることができるわけではありません。
残業を労働者に強制できるようにするためには、
まず就業規則に残業を命じる旨の記載が必要です。
過去の裁判例でも時間外労働を命じるためには
就業規則に「業務上の必要があるときは、
時間外・休日労働を命じる」旨の記載があることが必要だとしており、
この記載があれば労働者は正当な理由なく残業命令を拒否できなくなります。
会社は、社員の入社時に労働契約書を結びますが、
残業がある場合は、この契約書の中にも「残業がある」旨を明示することが、
法律で義務づけられていますので、忘れないようにしましょう。
以上のような手続きを行った場合、
従業員は、その残業命令が「正当なもの」であるかぎり、拒否できなくなります。
正当なものとは、次の条件を満たしているものをいいます。
1.36協定の範囲内の残業であること。
2.時間外労働をさせる業務上の必要性があること。
3.残業命令が社員の健康を害さないこと。
4.社員の生活設計(家族の保育や病人への配慮)を害さないこと。
5.社員が残業ができない理由を具体的に述べて拒否した場合、
その拒否理由に正当性があるかを考慮していること。
以上の要件が守られていれば、残業拒否は業務命令違反となり、懲戒処分も可能です。
配置転換を拒否されるとは

従業員に別部署への異動を命じたところ、
「そのような労働契約は結んでいない」
と拒否されました。
会社として
どのような対処をすればいいのでしょうか。
●人事異動とは?
会社が従業員の職務を変更したり、勤務場所の異動を命じたりすることを、
人事異動といいます。
人事異動については、就業規則に定めがあり、
また入社時に特別な条件をつけて雇用した者でない限り、会社に権利があります。
つまり、従業員は、人事異動の命令に従わなければならず、
それを拒否することは原則としてできません。
ただ例外もあります。
たとえば親の介護や育児などの理由から、遠くの支店に転勤できない、
残業の多い部署に行けないといった場合です。
社員に正当な理由がある場合、会社はこれに配慮しなければなりません。
ですから人事異動を拒否されたときは、
異動できない理由を本人から聞き、人事異動を強制するかどうかを、
判断するようにしましょう。
また業務に基づくものでない異動も認められません。
会社の恣意的な異動ではないか、上司の嫌がらせによる異動でないか、
確認することが必要です。
●人事異動の判例
判例では「勤務場所の変更」「社員の職務転換」については
"会社に権利がある"と判断されることが多いようです。
ただし技術者として雇った者をまったく関係のない経理に配属するのは、
必ずしも適法であるとは言えません。
「技術者としての能力がないから」と判断しても、すぐに職務を変えるのではなく、
「いく度となく指導・教育したが、能力向上のきざしがない」といった、証拠が必要です。
そのうえで本人と話し合い、合意を得たうえで異動を命じましょう。
いずれにせよ、異動を命じるときは、就業規則に異動についての定めが必要です。。
尚、出向については就業規則に出向を命じる旨の記載があり、
出向規程等で労働条件等について示されていれば、
必ずしも社員の同意を得る必要はないとしています(判例による)。
ただし転籍については、別会社に移籍することになるので社員の同意が必要です。
茶髪やひげをはやした従業員
従業員の中に、茶髪やあごひげをはやした者が増えてきて困っています。
中には、取引先と接する営業部員やお客様と接する販売部員もいて、
会社のイメージを損ないかねません。
身なりを改善させる手段はありますか。
●社員が守るべき服務規律とは?
社員の身なりが、会社として容認できる範囲を超えている場合は、
注意・指導を行って当然です。
直属の上司が改めるよう本人に伝えるようにしましょう。
それとともに就業規則の服務規律に
「服装・身なりは、常に清潔にし、不快感を与えないよう留意すること」
といった一文を入れておくことをおすすめします。
この一文があることによって、
改善されない場合は、正式な規律違反となり、
出勤停止などの懲戒に処することができるようになります。
それでも「個人の自由だ」というなら、解雇もありえます。
ただし、解雇する場合は、
社員の身なりが客観的に見て会社のイメージを損なっているという事実が必要です。
たとえば取引先から派手な髪型を指摘されたとか、お客様に服装が不快だといわれた等
・・・そのような事実があり、上司が注意・指導しても改善されないのであれば、
解雇の検討も仕方ありません。
●解雇するときは警告を!
顧客の印象を悪くする服装や身なりは、会社のイメージを損なうという意味で、
懲戒事由にあたりますが、
いきなり「解雇」というのは罰が重すぎます。
まずは・・・口頭注意⇒始末書の提出⇒出勤停止・・・といった過程を踏んだうえで、
それでも改善されないときは、
書面にて「○○日までに改善されないときは解雇する」と警告するといいでしょう。
また、上司の個人的な意見で服装や身なりを正させるのではなく、
あくまでも就業規則の服務規律に照らし、
「常識的な身だしなみをするように」と指導するようにします。
男性が女性の身なりを注意するときは、
言葉づかいによってはセクハラと受け止められることもあるので注意したいものです。
欠勤した従業員が有給を要求

会社を欠勤した従業員が、
「欠勤を、年次有給休暇と替えてほしい」
と要求してきました。
欠勤と有給休暇は趣旨が違うので認めないというと、
それは法違反ではないかといわれたのですが、本当に違法なのでしょうか。
●年次有給休暇とは?
年次有給休暇は、社員から"事前"に請求された場合には、与えなければなりせん。
しかし、欠勤後、請求されても振り返る必要はまったくありません。
社員とすれば欠勤は賃金カットにつながるので、有給休暇と振り替えたくなりますが、
法律上振り替えをしなければならないといった規定はなく、
欠勤分の賃金を給料から差し引いても、何の問題もありません。
ただ多くの会社は、慣例として有給休暇の事後振り替えを認めています。
病気などで仕方なく休んだ者に対し、欠勤を欠勤として扱い、
給料から賃金をカットするのは少し厳しいと思われるからです。
ですから、条件によっては有給休暇の事後振り替えを認めるのもいいと思います。
この場合、就業規則に年次有給休暇の事後振り替えについて、記載しておく必要があります。
ここを曖昧にしておくと、無断欠勤のような悪質な欠勤にまで、
年次有給休暇の振り替えを、認めなければならなくなります。
就業規則に、有給休暇の事後振り替えの規定を加えて置くといいでしょう。
退職後に重大な懲戒事由が発覚
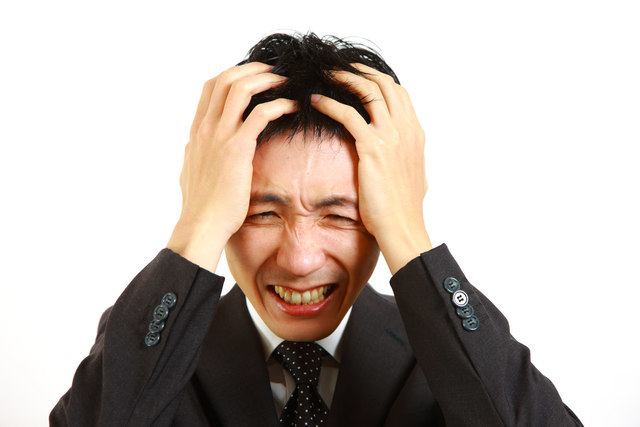
退職した社員が在職中に重大な社内情報を
他社に洩らしていたことが発覚しました。
本来なら懲戒処分としたいところなのですが、
すでに退職してしまっており
何もできません。
会社としてはただ泣き寝入りするしかないのでしょうか。
●退職後の懲戒処分は原則出来ません
就業規則の懲戒事由は、社員が現に在職している場合に有効です。
しかし、このケースでは、すでに社員が退職しています。
給料を減給するにも、本人は辞めているので減給しようがありませんし、
出勤停止処分や懲戒解雇もできません。
このような場合は、会社が被った損害の賠償を求めて、提訴するわけですが、
請求手続きは、費用的にも時間浪費という意味でも、会社にメリットがあるとはいえず、
結局は、泣き寝入りする会社が少なくないのは確かです。
●退職金の返還が可能
それでは、どのような対処法があるのでしょう。
社員が退職した後に懲戒事由にあたる不正が発覚したときは、
退職金の不支給、または減額で対処するというのが一般的です。
退職金をすでに支払ってしまったというときでも、
就業規則に「すでに支給した退職金があるときは、返還させることができる」
という一文があれば、返還を求めることができます。
この一文がないために、多くの会社が過去の裁判で敗訴し、
退職金の返還を求めることができませんでした。
そこで最近は、このような条文を就業規則(退職金規程)に入れ、
万一のときに退職金の返還をもって対処できるようにしているわけです。
退職従業員の機密情報漏えい

新商品を発売する前だというのに、競合会社が
すでに当社の新商品の情報を入手していました。
社内で調査をした結果、
数カ月前に退職した社員が、
退社後に情報を洩らしていた事が判明しました。
今後、このようなことが起こらないよう対処できないでしょうか。
●機密情報を保護する方法
会社の機密情報については、その重要性を社員に認識してもらうために、
服務規定とは別に、別項目を設けて規定しておきましょう。
そのさい
「従業員は、在職中はもちろん退職後においても、
職務上知り得た情報を社外に洩らしてはならない」と規定しておくことです。
就業規則に「機密情報の保護」を規定するときは、
どのようなものが機密情報といえるのかを、
できるだけ具体的に項目をあげて書くのがポイントです。
これに加え、
「機密情報は許可なく複写してはならないこと」
「情報の入った資料は持ち出してはならないこと」などを規定しておくと、
さらに情報流出を抑える効果が高まります。
●守秘義務誓約書を求める
個人情報などを扱う会社は、
就業規則に「機密情報の保護」の規定を設けるとともに、
必要な社員と「守秘義務誓約書」を取り交わすようにします。
誓約書の内容は
「私は、貴社を退職してからも、業務上知り得た技術上、営業上の有用な情報、
個人を識別できる情報を他に洩らしません。
もし、これに違反した場合は、
退職金の返還または損害賠償を請求されても異議はございません」といった内容にします。
こうする事で、現在はもちろん退社後においても、
情報の流出を抑える効果が期待できるだけではなく、
万一のときに損害賠償請求がしやすくなります。